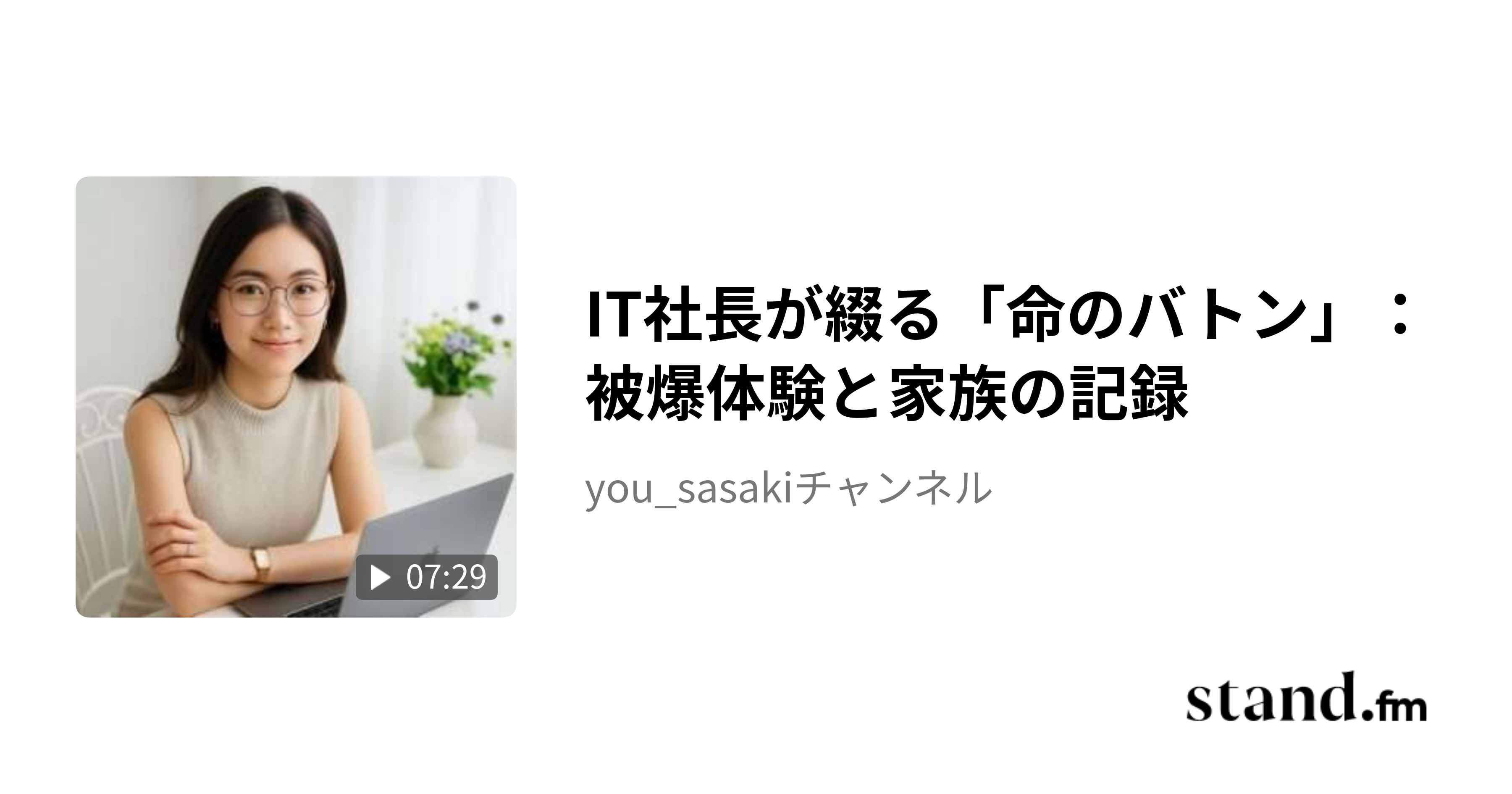IT企業 リミブレイク代表取締役の佐々木優です。2019年に創業し、現在社員15名の小さな会社を経営しています。
読み上げ音声
私の事は以下のプロフから👇
実は昨日の夜、また眠れませんでした。仕事のプレッシャーじゃありません。ネットで見つけたある記事が、ずっと頭から離れないんです。その記事とは…
101歳のおばあちゃんから1歳へ つむいできた「奇跡的な命」
広島で被爆した101歳の清水笑香さんの話。助産師をしている孫の増坂映里子さんが、その体験を記録して1歳の娘に残そうとしている。なんでこんなに心がざわつくのか、自分でもよく分からないまま、深夜にキーボードを叩いています。
朝日新聞が報じた「つむぐ」プロジェクトの重み
2025年の被爆者アンケート「つむぐ」について、私が読んだのは朝日新聞デジタルの記事でした。この名前を考えた人、相当悩んだんじゃないでしょうか。糸を紡ぐように、記憶を織り上げるように。
報道によると、全国11,000人に配布して、3,564人が回答。平均年齢86.1歳で、16.2%が代筆だったそうです。
この数字を見て、正直ゾッとしました。代筆が必要ということは、もう自分の手では書けない。そして86歳という年齢。計算すると、10年後には…
「語れなかった。でも孫には伝えたい」
「70年沈黙してきたが、やっと言葉にできた」
なんで70年も黙っていたんだろう。
そして、なぜ今になって話し始めたんだろう。
私の祖父も戦争を経験していました。でも生前、戦争の話をしたのは数回だけ。それも断片的な話で、詳しく聞こうとすると「若い子には分からんよ」と話題を変えられました。「つらいことは忘れた方がいい」が口癖でした。
祖父が亡くなったのは私が大学2年の時。ちょうど就活で忙しくて、最期の日も会えませんでした。今思えば、私がもっと粘り強く聞いていれば…いや、これって結局後悔しても仕方ないんですけどね。でも後悔するんです、どうしても。

“語らなかった”じゃなく“語れなかった”んだよね…86歳の声に胸がぎゅっとなった
80歳で語り始めた清水さんのタイミング

清水笑香さんが被爆したのは1945年、爆心地から1.6km。記事によると、家族や知人を一瞬で失ったとありました。想像できませんよね、そんな体験。
そして60年間沈黙。80歳になってから語り始めた。
「語ることは怖かった。でも、孫の代には伝えたかった」
この一文を読んだ時、電車の中だったんですが涙腺が緩みました。周りの目が気になって必死に堪えましたが。

「語ることは怖かった。でも、孫の代には伝えたかった」
この想いは、私達には絶対に理解できない!この想いだけは戦争を体験し被爆した人だけが、一生抱え続ける想い。
なぜ孫の代なのか。子どもの代じゃダメだったのか。きっと、直接的すぎて話せなかったんでしょうね。子どもに話すということは、自分の痛みを直接手渡すようなもの。でも孫なら、少し距離があるから話しやすい。
私も5歳の姪がいます。まだ「ママ」「パパ」程度しか話せませんが、この子が大きくなった時、私は自分の人生をどう伝えるんだろう。起業時の借金地獄の話?システム障害で3日間眠れなかった話?それとも、もっと深い部分の話?
助産師という職業が持つ特別な視点
増坂映里子さんは助産師。毎日、命の誕生に立ち会っている。
「祖母の命がつながって、私が生まれ、娘がいる。助産師という立場だからこそ、命の記録の大切さを実感します」
これ、本当にすごいと思うんです。命を取り上げる仕事をしている人が、自分のルーツを辿っている。生と死、始まりと継承が一つの線でつながっている。
私たちIT業界って、どうしても「新しいもの」ばかり追いかけがちです。最新のフレームワーク、新しいクラウドサービス、AI技術。「古いシステムはレガシー」って言って、リプレイスを提案する。
でも増坂さんを見ていると、「古いもの」を大切にすることの意味を改めて考えさせられます。システムでも、古いからといって価値がないわけじゃない。そこに蓄積されたデータや運用ノウハウには計り知れない価値がある。人間の記憶も同じなのかもしれません。
教育現場での反応―「自分ごと」になる瞬間

この記録、もう教育現場で使われているらしいです。NHKの報道で知ったのですが、中学校の道徳で音読したり、小学校で平和学習のワークショップに使ったりしているそうです。
先生方の感想も印象的でした。
「生徒たちが”自分ごと”として命を捉え始めた」 「教科書だけでは不十分。リアルな家族史が心を動かす」
そうなんです、「自分ごと」なんです。
私も学生時代、平和教育を受けました。広島の原爆資料館にも修学旅行で行きました。でも正直、どこか他人事でした。感想文は書いたけれど、それで終わり。
でも家族の話となると全然違う。血がつながっている。自分に直接関わってくる話だから、リアリティが段違いです。
うちの会社でも新人研修で「自分の家族について話す」時間を作っているんですが、みんな表情が変わるんですよね。普段はクールな新人も、家族の話になると急に生き生きとする。
私なりの「記録」実験―試行錯誤の日々
この記事を読んでから、私も家族の記録を始めました。といっても、まだ手探り状態ですが。
録音アプリで失敗した話
最初はiPhoneの標準録音アプリを使って、母との会話を録音しようとしました。でも「録音するね」と言った途端、母が緊張してしまって。普段なら自然に出てくる昔話も、なんだかインタビューみたいになってしまいました。
と逃げられる始末。
今は録音していることを伝えずに、自然な会話の中で記録しています。倫理的にどうなのかという問題もありますが…まあ、家族なので許してもらいましょう。後で「実は録音してた」と白状するつもりです。

録音するって言ったら母が固まった…今はこっそり自然に残してる。あとで白状予定😅
古いアルバムの威力
実家にある古いアルバムを見ながら話を聞くのは効果的でした。写真があると、記憶が蘇るみたいです。「この時はね…」と話が弾みます。
特に昭和40年代の白黒写真を見ながらの話は面白かった。当時の生活の様子、近所付き合い、今とは全然違う価値観。
「この頃は冷蔵庫がなくて、氷屋さんが来るのを待ってたのよ」 「お父さん(私の祖父)は自転車で片道1時間かけて通勤してた」
「へえ、そんな時代だったんだ」という発見の連続でした。
デジタル化の課題とツール選び
IT企業の社長らしく、音声ファイルも写真もGoogle Driveに保存していますが、これが意外と大変。ファイル名をどうするか、フォルダ構成をどうするか。
今は以下のような構成にしています:
- 家族記録/
- 音声/
- 2025年/
- 01_母との会話_昭和40年代の生活.m4a
- 02_母との会話_祖父の仕事の話.m4a
- 2025年/
- 写真/
- デジタル化済み/
- 元データ/
- 音声/
Adobe ScanとかCamScannerとか、いろんなスキャンアプリを試しましたが、古い写真の場合はEPSONのスキャナーでじっくりスキャンした方が綺麗でした。
音声の文字起こしには、Google Driveの音声入力機能とOtter.aiを併用しています。精度は8割程度ですが、後で見返すには十分です。
地域の高齢者施設での意外な発見
会社近くの「陽だまりの里」という高齢者施設で、月1回ボランティアをしています。といっても、お話を聞かせてもらうだけですが。
先月聞いた90歳の田中さん(仮名)の話が忘れられません。戦時中の食糧難の話、疎開先での体験、復員してからの苦労。1時間があっという間でした。
と喜んでくださいました。私も勉強になりましたし、互いに良い時間だったと思います。
でも、こういう場に来る若い人って本当に少ないんです。施設の職員さんに聞いたら、「ボランティアの平均年齢は65歳です」とのこと。みんな忙しいのは分かりますが、もったいないなと思います。
特に印象的だったのは、田中さんがスマホで孫の写真を見せてくれた時の表情。すごく嬉しそうで、でも少し寂しそうでもあって。
「この子たちに戦争の話をしても、ピンとこないみたいでね」
確かに、今の若い世代にとって戦争は歴史の教科書の中の出来事。でも、おじいちゃんの体験として聞けば、きっと違うはずなんですが。
社内での予想外の反応
この話を社内の朝礼でしたところ、思いがけない反応がありました。
「私も祖父の話を聞いてみたい」
「実は昔、祖母から戦争の話を聞いたことがある」
「家族の写真をデジタル化してみようかな」
特に印象的だったのは、入社2年目の山田さん(仮名)のエピソード。祖父の戦争体験を聞いて作文にしたところ、家族みんなが泣いたという話でした。
「普段あまり話さない祖父が、その日は夜遅くまで昔の話をしてくれました。
『孫がこんなに真剣に聞いてくれるとは思わなかった』って」
記録することで、家族の絆が深まったんでしょうね。
それ以来、うちの会社では「家族史プロジェクト」というのが自然発生的に始まりました。希望者だけですが、毎月1回、家族から聞いた話をシェアする会を開いています。仕事に直接関係ないかもしれませんが、チームの結束は確実に強くなりました。
テクノロジーの限界と可能性
IT企業の社長として、技術的な側面も考えてみました。
最近のAI音声認識技術はかなり精度が高くなっています。Google CloudのSpeech-to-Text APIやAWSのTranscribeなどを使えば、高齢者の方の話も比較的正確に文字起こしできます。
ZoomやGoogle Meetの録画機能を使えば、遠く離れた家族とも記録を共有できる。実際、コロナ禍で実家に帰れない間、ビデオ通話で祖母の話を聞いていた友人もいます。
でも、技術はあくまで道具。大切なのは「聞く」という行為そのものです。相手の目を見て、心を込めて聞く。時には涙ぐんだり、一緒に笑ったり。その時間自体に意味がある。
最新のAIチャットボットを使えば、質問を自動生成してくれるサービスもあります。でも機械的な質問では、本当に大切な話は引き出せないと思います。
技術は後からついてくるもの。まずは人と人の関係性があって、そこに技術を少し加えることで、より多くの人に伝えられるようになる。そんな順番なんじゃないでしょうか。

AIの力もすごいけど…やっぱ一番大事なのは“心を込めて聞く”ってことなんだよね🤖💬❤️
なぜIT社長の私がこんなに「記録」にこだわるのか
正直、自分でもよく分からないんです。なぜこんなに「記録」にこだわるのか。
システム開発では、どんな小さな変更でもログを残します。バックアップは必須。データの整合性を保つためのトランザクション管理。「記録」は私たちの仕事の基本中の基本です。
でも人間の記憶となると、案外軽視しがち。「覚えているからいいや」「今度聞けばいいや」。そうして大切な話を聞き逃してしまう。
もしかしたら、祖父の話をもっと聞いておけばよかったという後悔があるからかもしれません。あるいは、5歳の姪に何を残してあげられるかを考えるからかもしれません。
IT業界って、すべてがめまぐるしく変わります。3年前の技術が古臭く感じられる世界。React、Vue、Next.js…新しいフレームワークが次々に登場して、学習が追いつかない。
そんな中で仕事をしていると、「変わらないもの」「受け継がれるもの」に対する憧れみたいなものが生まれるのかもしれません。
30代という微妙な立ち位置

私たちの世代って、微妙な位置にいると思います。
戦争体験者の証言を直接聞ける、おそらく最後の世代。同時に、デジタル技術をネイティブに使いこなせる世代でもある。
SNSで情報を発信することにも慣れているし、クラウドサービスを使ったデータ保存も当たり前。でも一方で、アナログな温かみも理解できる。
この両方の特徴を活かして、過去と未来をつなぐ役割を担えるんじゃないでしょうか。少し大げさかもしれませんが、そんな使命感みたいなものを感じています。
実際、うちの会社のお客さんの中にも「デジタル化はしたいけど、温かみは失いたくない」という要望をお持ちの方が多いです。特に地域の中小企業や老舗企業では、「伝統を守りながら、新しい技術も取り入れたい」というジレンマを抱えています。
家族の記録も同じかもしれません。最新の技術を使って効率よく保存はしたいけれど、機械的になりすぎるのは嫌。そのバランスが大切なんでしょうね。
完璧を求めず、まず始めること
最後に言いたいのは、完璧である必要はないということ。
私の記録も、まだまだ試行錯誤の段階です。録音に失敗することもあるし、整理が追いつかないこともある。先日は間違って重要なファイルを削除してしまい、慌ててバックアップから復旧しました。
でも、何もしないよりはマシだと思っています。
清水笑香さんの101年の人生も、増坂映里子さんの記録活動も、きっと完璧ではないはず。でも、その不完全さこそが人間らしくて、温かみがあって、心に響くんじゃないでしょうか。
あなたの家族にも、きっと素晴らしい物語があります。それを完璧に記録する必要はありません。ただ、少しだけ耳を傾けてみませんか。
スマホの録音機能だけでも十分です。高価な機材は要りません。大切なのは「聞こう」という気持ちです。
101歳から1歳へ。命のバトンは、今この瞬間も受け継がれています。
この記事を書きながら、改めて思いました。技術は確かに便利で、私たちの生活を豊かにしてくれます。でも、最も大切なのは人と人とのつながり、そして記憶を受け継ぐことなのかもしれません。
明日また、母に電話してみようと思います。今度は録音のことは内緒で。
著者プロフィール
参考情報
- 2025年の被爆者アンケート「つむぐ」については、朝日新聞デジタル等の報道を参考
- 高齢者施設でのボランティア活動については、筆者の実体験に基づく
- IT技術に関する情報は2025年1月時点のもの
関連リンク
#家族史 #被爆体験 #記録の大切さ #IT社長の想い #命のバトン #平和学習 #デジタルアーカイブ #シニアの語り #体験をつなぐ #祖父母の話