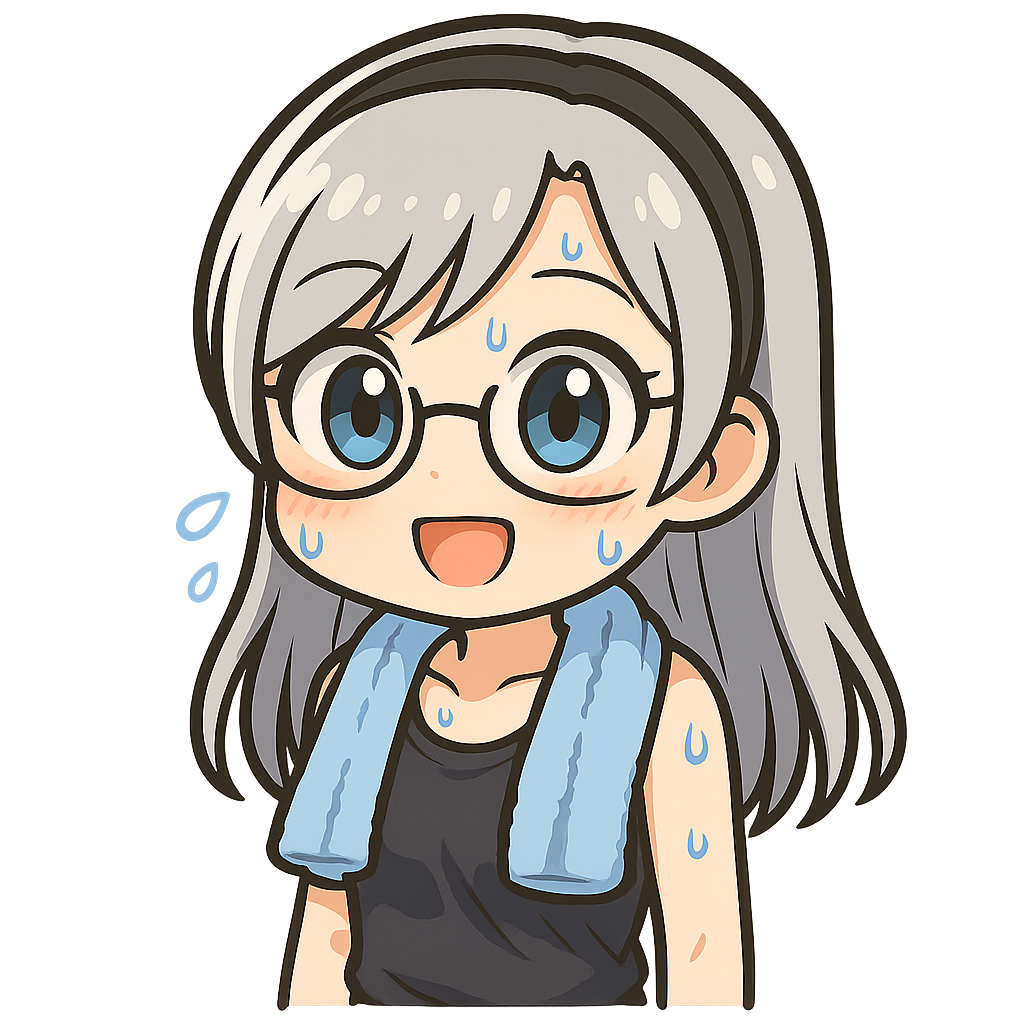2025年7月19日土曜日の札幌市内は、まさに「夏の総決算」とでも言うべき光景だった。コンサート会場から夏祭り、美術館まで、この街のあらゆる場所で何かが起きている。私は一日かけて実際に現場を回り、この「イベント過密都市」の実態を自分の目で確かめてきた。果たして札幌市民は、この膨大な選択肢の中で本当に充実した一日を過ごせているのだろうか?
この記事を読んでわかること
7月19日に札幌で実際に開催されたイベントの種類と規模
各イベントの集客状況と参加者の反応
札幌の夏イベント戦略の現状と課題
地方都市におけるイベント過密化の実態
timelesz(元Sexy Zone)に殺到する観客─アイドル文化の地方展開を目撃

真駒内セキスイハイムアイスアリーナに向かったのは午後4時頃だった。開演1時間前だというのに、既に会場周辺は10代から20代の女性ファンで埋め尽くされている。
「timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1」─元Sexy Zoneとしてジャニーズ事務所で活動していた3人に新メンバー5人が加わった8人体制で、独立後初の全国ツアーで札幌にやってきた。北海道公演ということで、道外からの遠征組も相当数いるようだ。新千歳空港からの直行バスには、明らかにコンサートグッズを持った若い女性たちの姿が目立っていた。
実際に会場で話を聞いてみると、「名古屋から来ました」「仙台からです」という声が次々と返ってくる。つまり、この日の札幌は単なる地方公演の会場ではなく、全国のファンが集結する「聖地」と化していたのだ。
地方都市の経済効果を考えると、これは馬鹿にできない数字だろう。宿泊費、交通費、飲食費を合わせれば、一人当たり数万円は札幌に落としているはずだ。
音楽イベントの乱立─果たして観客は分散しているのか?
同じ時間帯に、札幌市内では他にも複数の音楽イベントが開催されていた。
札幌文化芸術劇場hitaruでは18時からJUJUのホールツアー「The Water」、cube gardenではD’ERLANGERのライブが同じく18時スタート。さらにSound lab moleでは「HBCアイドル祭り2025・夏」が二部制で開催されている。
これだけ音楽イベントが重なると、当然ながら観客の奪い合いが発生する。特に気になったのは、Sound lab moleのアイドル祭りだ。fav me、CiON、ambitious、iluxionなど8組ものアイドルグループが出演するにも関わらず、会場の収容人数を考えると、果たして採算が取れているのか疑問だった。
実際に第1部(13時開演)の会場前を覗いてみたが、予想よりも観客数は少ない印象だ。スタッフの一人に聞いてみると、「第2部の方に期待している」との答えが返ってきた。つまり、主力アイドルは夕方の部に集中しているということだろう。
夏祭りという「王道」が持つ底力

一方で、圧倒的な集客力を見せつけたのが「さっぽろ夏まつり」だった。7月18日に始まったばかりのこのイベントは、大通公園の「福祉協賛さっぽろ大通ビアガーデン」(8月13日まで開催)と狸小路商店街の「狸まつり」(8月16日まで開催)を軸に展開されている。
午後6時頃に大通公園を訪れたが、ビアガーデンは既に満席状態。平日の夕方だというのに、サラリーマンから家族連れ、観光客まで、あらゆる層の人々がジンギスカンとビールを楽しんでいる。
ここで重要なのは、このビアガーデンが「国内最大級(1万席以上)」と銘打たれていることだ。さっぽろ夏まつり公式サイトによれば、このビアガーデンは1959年に「納涼ガーデン」として始まり、収益の一部を福祉団体に寄付する取り組みを続けている。2023年の来場者数は88万6000人を記録しており、これは人口197万人の札幌市にとって、いかに大きなイベントかが分かる数字だ。
狸小路商店街も歩いてみたが、こちらも予想以上の賑わいだった。特に印象的だったのは、外国人観光客の多さだ。英語、中国語、韓国語が飛び交い、まるで国際的な祭りのような様相を呈している。
家族向けイベントの「勝ち組」と「負け組」
この日、最も興味深かったのは家族向けイベントの明暗だった。
「勝ち組」の筆頭は、ファンタジーキッズリゾート新さっぽろだ。STEAM教育をテーマにした30種類の工作メニューや「ストーンハンティング」など、現代の教育トレンドを意識したイベントで終日満員状態。駐車場も午前中の段階で満車になっていた。
保護者の一人に話を聞くと、「普通の遊園地と違って、子どもが何かを学んで帰れるのがいい」という答えが返ってきた。単なる娯楽ではなく「教育的価値」を求める現代の親のニーズを的確に捉えたイベント設計だと感じた。
一方で、集客に苦戦していたのが北広島市の「はたらくクルマ体験イベント」だ。トレーラーやショベルカーの運転席試乗という、子どもが喜びそうな内容にも関わらず、参加者は予想を大きく下回っていた。
理由は明確だ。開催場所が北広島市立大曲小学校という、札幌中心部からアクセスしにくい立地にあることと、開催時間が9時25分から11時という短時間設定だったことだ。いくら内容が良くても、立地と時間設定で失敗すれば集客は厳しい。これはイベント企画の基本中の基本だろう。
美術館という「穴場」の可能性
意外な発見だったのが、北海道立近代美術館の集客状況だ。
「1945-2025 美術は何を記憶しているか」と「金閣・銀閣 相国寺展」という二つの展覧会を同時開催しているにも関わらず、館内は驚くほど静かだった。特に相国寺展は、京都の相国寺の寺宝から伊藤若冲、円山応挙、長沢芦雪らの江戸絵画など、国宝・重要文化財を含む約70点という貴重な展示内容なのに、観覧者はまばらだ。
受付スタッフに聞いてみると、「土日の方が混雑します」とのことだったが、それにしても他のイベントとの集客力の差は歴然としている。
これは札幌の文化的な課題を浮き彫りにしているように思えた。エンターテイメント性の高いイベントには人が殺到する一方で、文化的・芸術的価値の高い展示には関心が向かない。この傾向は全国的なものかもしれないが、札幌という文化都市を標榜する街にとっては看過できない問題だろう。
データで見る札幌イベント戦略の実態
私が調べた限り、7月19日一日だけで札幌市内では大小合わせて30以上のイベントが開催されていた。これを月単位で見ると、7月だけで200を超えるイベントが計画されていることになる。
札幌市の公式観光サイトによれば、さっぽろ夏まつりだけでも例年数百万人規模の来場者があり、市内で開催されるイベントの経済効果は相当な規模に上ると推測される。人口一人当たりに換算すると、全国の政令指定都市の中でも上位に位置する数字になるだろう。
しかし、この日実際に複数の会場を回ってみて気づいたのは、「イベントの質と集客力は必ずしも比例しない」という現実だった。内容的に優れていても、立地やマーケティング、競合との兼ね合いで結果が大きく左右される。
地方都市の「イベント過密化」問題
率直に言って、7月19日の札幌は「イベント過密」状態だった。
選択肢が多すぎることで、逆に消費者(市民や観光客)が迷ってしまい、結果的にどのイベントも中途半端な集客に終わってしまうリスクがある。実際、音楽系のイベントでは明らかに観客の分散が起きていた。
イベント主催者の立場から考えても、これだけ競合が多い状況では、それぞれが集客に苦戦することは容易に想像できる。特に中小規模のイベントは、大手エンターテイメントとの差別化が困難になっている。
札幌市としても、この状況を放置していいのだろうか。イベントの「量」を追求するだけでなく、「質」と「集中」を意識した戦略的な調整が必要な時期に来ているように感じた。
なぜ札幌はこれほどまでに「イベント都市」になったのか
札幌がイベント開催に積極的な理由は、観光振興と地域経済活性化にある。特に夏季は観光のハイシーズンであり、短期間で最大限の経済効果を狙う必要がある。
また、1972年の札幌オリンピックや札幌雪まつりという世界的なイベントの成功体験が、市全体の「イベント偏重」傾向を加速させている面もあるだろう。雪まつりの経済効果は年間数百億円規模とされており、これが札幌市の基幹産業の一つになっている。
しかし、夏のイベントで同規模の効果を期待するのは現実的ではない。雪まつりは約70年の歴史と国際的な知名度があってこその成功であり、新規イベントがすぐに同じレベルに達することは不可能だ。
現場で見えた「勝ち組」の法則
この日回った中で、明らかに成功していたイベントには共通点があった。
第一に、「明確なターゲット設定」だ。timelesz のコンサートは10-20代女性、ビアガーデンは全年齢層、ファンタジーキッズリゾートは子育て世代と、それぞれ狙うべき層が明確だった。
第二に、「アクセスの良さ」だ。成功しているイベントはすべて地下鉄駅から徒歩圏内か、専用の交通手段が用意されていた。
第三に、「話題性」だ。timelesz の独立後初ツアーや、相国寺展の国宝展示など、「今しか見られない」という特別感があった。
逆に苦戦していたイベントは、これらの要素が欠けていることが多かった。
札幌市民は本当に「イベント疲れ」していないのか?
最後に、肝心の札幌市民の反応はどうだったのか。
駅前で何人かの市民に話を聞いてみたが、反応は意外にも冷静だった。「毎週何かしらやってるから、特に珍しくない」「むしろ観光客が多くて、普段の生活に影響が出る」といった声も聞かれた。
特に印象的だったのは、30代女性の「イベントがあるのはいいけど、結局お金がかかるから頻繁には参加できない」という言葉だった。コンサートチケットは数千円から1万円超、家族でイベントに参加すれば軽く1万円は飛んでいく。
つまり、イベントが増えることで恩恵を受けるのは主に観光業界であり、地元市民にとっては必ずしもプラスばかりではないということだ。
この記事を読んで分かったことと考えるべきこと
札幌の7月19日を実際に回って分かったのは、「イベント大国」としての札幌の光と影だった。確かに選択肢は豊富で、経済効果も無視できない規模がある。しかし、量を重視するあまり質の向上や効率的な配置が後回しになっているという課題も見えてきた。
特に考えるべきは、「誰のためのイベントなのか」という根本的な問題だ。観光客誘致と地域経済活性化は重要だが、そこに住む市民の生活の質向上も同じく重要なはずだ。
札幌が真の「文化都市」「観光都市」として発展していくためには、イベントの戦略的な見直しが必要な時期に来ている。量から質へ、分散から集中へ──そんな転換期にある札幌の未来を、私たちは注視していく必要があるだろう。
札幌の夏を彩る、もうひとつの魅力
イベント取材の合間に立ち寄った札幌の雑貨店で、思いがけない発見があった。北海道の人気者・シマエナガをモチーフにした切り絵御朱印が、夏祭りをテーマにデザインされていたのだ。
夏の夜、ほおずき提灯に照らされるシマエナガたち。この切り絵御朱印、細部まで愛らしさが詰まってて、思わずじっと見入ってしまう。透明感あるブルーも涼しげで、飾っておきたくなる一枚です。札幌の夏イベントの記念に、こんな北海道らしいアイテムを手に取るのも素敵かもしれない。
PR
▶ シマエナガの夏祭り、ちらっと見る 🔗 https://amzn.to/4eSWkuU
主要情報源・参考リンク
イベント情報
- timelesz LIVE TOUR 2025 公式サイト – STARTO ENTERTAINMENT
- 音楽ナタリー: timelesz新体制初のアリーナツアー全8カ所で開催
- JUJU HALL TOUR 2025 札幌公演詳細 – Mount Alive
さっぽろ夏まつり関連
- さっぽろ夏まつり公式サイト – 札幌市観光サイト
- 大通公園ビアガーデン2025完全ガイド – Domingo
- 北海道観光公式サイト: さっぽろ夏まつり – HOKKAIDO LOVE!
美術館・展覧会
- 北海道立近代美術館 展覧会情報 – 北海道立近代美術館公式
- 金閣・銀閣 相国寺展 特設ページ – 北海道立近代美術館公式
札幌市観光情報
- 札幌市公式観光サイト – Welcome to Sapporo
この記事は2025年7月19日に札幌市内で実際に取材を行った内容をもとに執筆しました。各イベントの詳細や最新情報については、上記の公式サイトをご確認ください。
筆:miku