



佐々木 優です。
今日一日、ITニュースを追いかけてて思ったんですが、明日の参院選、マジでIT業界と株価に直結する話になってきてますね。
まず、今日目についたのがラピダスの話。昨日発表された2ナノ半導体の試作成功なんですが、これ、政治と絡めて考えると結構ヤバい。
私、大学で半導体の研究やってたんで分かるんですが、2ナノって本当にとんでもない技術なんです。で、これが成功したタイミングで明日選挙って…偶然にしては出来すぎてる。
政府の半導体戦略、今回の選挙結果次第で大きく変わる可能性があるじゃないですか。与党が勝てば予算拡大、負ければ見直し。ラピダスの量産計画にも影響するかも。
で、今日もう一つ気になったのが、自動車メーカーの値上げの続報。
これ、IT業界にも無関係じゃないんですよ。うちの会社、アメリカ向けのSaaSサービス展開してるんですが、トランプ政権の関税政策の影響でサーバー調達コストが上がってる。クラウドサービスの料金も上昇圧力がかかってきてて、正直厳しい。
ボルボが業績予想を撤回したニュースを見た時、「他人事じゃないな」って思いました。グローバル展開してる企業は、みんな同じような状況だと思います。
そういえば、Netflixの好決算のニュースも今日チェックしてたんですが、これで思い出したことが。
実は私、個人的にNetflix株を少し持ってるんです。今回の決算で利益出て、正直嬉しかった。でも同時に、「日本のコンテンツ産業、大丈夫?」って心配にもなりました。
IT業界にいると、アメリカ企業の成長スピードを痛感するんですよね。政治の安定性とか、スタートアップへの投資環境とか、日本とアメリカの差を感じる場面が多い。明日の選挙結果次第で、この辺りの政策も変わってくるかもしれません。
今日、IT関連のSlackチャンネルで一番話題になってたのが、日本生命の情報流出問題。
「逆流厳禁」って書いてバレないようにするって、セキュリティ業界の人間からしたら「何それ?」って感じです。大学生のレポートじゃないんだから。
うちの会社でも、GDPR対応とかで年間どれだけセキュリティにコストかけてると思ってるんだって話。こういう杜撰な管理をする大企業があると、業界全体の信頼が損なわれる。
金融庁の動向次第では、IT業界にも影響が波及する可能性があります。データガバナンスの規制が厳しくなるかもしれない。
関西電力の美浜原発計画のニュースも、IT業界には重要なんです。
データセンター事業やってる身としては、電力の安定供給と料金は死活問題。再生可能エネルギーだけでは、正直まだ安定性に不安がある。原発の是非は複雑な問題ですが、電力政策は選挙の重要な争点の一つですね。
クラウドサービスの普及で、電力消費量は右肩上がりです。AIの学習とかで、サーバーの電力消費も増加してる。エネルギー政策と IT政策は、もう切り離せない関係になってます。
G20財務相会議でアメリカが欠席してるのも気になります。
国際協調の枠組みが揺らぐと、グローバルなIT企業にとってはマイナス。規制の統一化とか、国際的なデータ移転の枠組みとか、こういう場で議論されることが多いんです。
アメリカの一国主義が強まると、IT業界のグローバル展開にも影響してきます。
今日一日のニュースを見てて思ったのは、IT業界と政治の関係がますます密接になってるってこと。
| 分野 | 選挙への関心度 | IT業界への影響 |
|---|---|---|
| 半導体政策 | 高 | 直接的に大きい |
| エネルギー政策 | 高 | データセンター運営に重要 |
| 国際協調 | 中 | グローバル展開に影響 |
| データガバナンス | 中 | 規制強化の可能性 |
正直なところ、来週の株価がどう動くかは読めません。でも、IT関連株は政治の影響を受けやすくなってるのは間違いない。
最後に、IT業界で働く皆さんに言いたいことが。
私たちの業界、政治と無関係だと思ってる人も多いと思います。でも、実際は規制、予算、国際関係、すべてが技術開発や事業展開に影響してくる。
明日の選挙、「自分には関係ない」って思わずに、投票に行ってもらえたら。IT業界の未来も、政治と無関係じゃないですから。
私たちの年金だって株式市場で運用されてるし、転職市場も政治の安定性に左右される。エンジニアだからって、政治に無関心でいられる時代じゃないと思います。
金曜の夜に政治と経済の話を書くのも何ですが、今日のニュースを見てて、どうしても書きたくなりました。
IT業界にいると、技術のことばかり考えがちですが、結局はビジネス環境や政治情勢が技術の方向性を決めることも多い。ラピダスの成功も、トランプ関税の影響も、すべて政治と経済が絡んでる。
明日の選挙結果が、来週のIT関連株にどう影響するか。月曜日の朝が楽しみのような、怖いような。
とりあえず、週末はゆっくり休んで、月曜日に備えます。皆さんも良い週末を。
佐々木 優
P.S. 今日、会社の若手エンジニアに「選挙行く?」って聞いたら、「IT業界と関係あるんですか?」って返されました。関係ありまくりです。この記事、そんな彼らに読んでもらいたくて書きました。
筆:佐々木 優
2025年7月19日土曜日の札幌市内は、まさに「夏の総決算」とでも言うべき光景だった。コンサート会場から夏祭り、美術館まで、この街のあらゆる場所で何かが起きている。私は一日かけて実際に現場を回り、この「イベント過密都市」の実態を自分の目で確かめてきた。果たして札幌市民は、この膨大な選択肢の中で本当に充実した一日を過ごせているのだろうか?
この記事を読んでわかること
7月19日に札幌で実際に開催されたイベントの種類と規模
各イベントの集客状況と参加者の反応
札幌の夏イベント戦略の現状と課題
地方都市におけるイベント過密化の実態

真駒内セキスイハイムアイスアリーナに向かったのは午後4時頃だった。開演1時間前だというのに、既に会場周辺は10代から20代の女性ファンで埋め尽くされている。
「timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1」─元Sexy Zoneとしてジャニーズ事務所で活動していた3人に新メンバー5人が加わった8人体制で、独立後初の全国ツアーで札幌にやってきた。北海道公演ということで、道外からの遠征組も相当数いるようだ。新千歳空港からの直行バスには、明らかにコンサートグッズを持った若い女性たちの姿が目立っていた。
実際に会場で話を聞いてみると、「名古屋から来ました」「仙台からです」という声が次々と返ってくる。つまり、この日の札幌は単なる地方公演の会場ではなく、全国のファンが集結する「聖地」と化していたのだ。
地方都市の経済効果を考えると、これは馬鹿にできない数字だろう。宿泊費、交通費、飲食費を合わせれば、一人当たり数万円は札幌に落としているはずだ。
同じ時間帯に、札幌市内では他にも複数の音楽イベントが開催されていた。
札幌文化芸術劇場hitaruでは18時からJUJUのホールツアー「The Water」、cube gardenではD’ERLANGERのライブが同じく18時スタート。さらにSound lab moleでは「HBCアイドル祭り2025・夏」が二部制で開催されている。
これだけ音楽イベントが重なると、当然ながら観客の奪い合いが発生する。特に気になったのは、Sound lab moleのアイドル祭りだ。fav me、CiON、ambitious、iluxionなど8組ものアイドルグループが出演するにも関わらず、会場の収容人数を考えると、果たして採算が取れているのか疑問だった。
実際に第1部(13時開演)の会場前を覗いてみたが、予想よりも観客数は少ない印象だ。スタッフの一人に聞いてみると、「第2部の方に期待している」との答えが返ってきた。つまり、主力アイドルは夕方の部に集中しているということだろう。

一方で、圧倒的な集客力を見せつけたのが「さっぽろ夏まつり」だった。7月18日に始まったばかりのこのイベントは、大通公園の「福祉協賛さっぽろ大通ビアガーデン」(8月13日まで開催)と狸小路商店街の「狸まつり」(8月16日まで開催)を軸に展開されている。
午後6時頃に大通公園を訪れたが、ビアガーデンは既に満席状態。平日の夕方だというのに、サラリーマンから家族連れ、観光客まで、あらゆる層の人々がジンギスカンとビールを楽しんでいる。
ここで重要なのは、このビアガーデンが「国内最大級(1万席以上)」と銘打たれていることだ。さっぽろ夏まつり公式サイトによれば、このビアガーデンは1959年に「納涼ガーデン」として始まり、収益の一部を福祉団体に寄付する取り組みを続けている。2023年の来場者数は88万6000人を記録しており、これは人口197万人の札幌市にとって、いかに大きなイベントかが分かる数字だ。
狸小路商店街も歩いてみたが、こちらも予想以上の賑わいだった。特に印象的だったのは、外国人観光客の多さだ。英語、中国語、韓国語が飛び交い、まるで国際的な祭りのような様相を呈している。
この日、最も興味深かったのは家族向けイベントの明暗だった。
「勝ち組」の筆頭は、ファンタジーキッズリゾート新さっぽろだ。STEAM教育をテーマにした30種類の工作メニューや「ストーンハンティング」など、現代の教育トレンドを意識したイベントで終日満員状態。駐車場も午前中の段階で満車になっていた。
保護者の一人に話を聞くと、「普通の遊園地と違って、子どもが何かを学んで帰れるのがいい」という答えが返ってきた。単なる娯楽ではなく「教育的価値」を求める現代の親のニーズを的確に捉えたイベント設計だと感じた。
一方で、集客に苦戦していたのが北広島市の「はたらくクルマ体験イベント」だ。トレーラーやショベルカーの運転席試乗という、子どもが喜びそうな内容にも関わらず、参加者は予想を大きく下回っていた。
理由は明確だ。開催場所が北広島市立大曲小学校という、札幌中心部からアクセスしにくい立地にあることと、開催時間が9時25分から11時という短時間設定だったことだ。いくら内容が良くても、立地と時間設定で失敗すれば集客は厳しい。これはイベント企画の基本中の基本だろう。
意外な発見だったのが、北海道立近代美術館の集客状況だ。
「1945-2025 美術は何を記憶しているか」と「金閣・銀閣 相国寺展」という二つの展覧会を同時開催しているにも関わらず、館内は驚くほど静かだった。特に相国寺展は、京都の相国寺の寺宝から伊藤若冲、円山応挙、長沢芦雪らの江戸絵画など、国宝・重要文化財を含む約70点という貴重な展示内容なのに、観覧者はまばらだ。
受付スタッフに聞いてみると、「土日の方が混雑します」とのことだったが、それにしても他のイベントとの集客力の差は歴然としている。
これは札幌の文化的な課題を浮き彫りにしているように思えた。エンターテイメント性の高いイベントには人が殺到する一方で、文化的・芸術的価値の高い展示には関心が向かない。この傾向は全国的なものかもしれないが、札幌という文化都市を標榜する街にとっては看過できない問題だろう。
私が調べた限り、7月19日一日だけで札幌市内では大小合わせて30以上のイベントが開催されていた。これを月単位で見ると、7月だけで200を超えるイベントが計画されていることになる。
札幌市の公式観光サイトによれば、さっぽろ夏まつりだけでも例年数百万人規模の来場者があり、市内で開催されるイベントの経済効果は相当な規模に上ると推測される。人口一人当たりに換算すると、全国の政令指定都市の中でも上位に位置する数字になるだろう。
しかし、この日実際に複数の会場を回ってみて気づいたのは、「イベントの質と集客力は必ずしも比例しない」という現実だった。内容的に優れていても、立地やマーケティング、競合との兼ね合いで結果が大きく左右される。
率直に言って、7月19日の札幌は「イベント過密」状態だった。
選択肢が多すぎることで、逆に消費者(市民や観光客)が迷ってしまい、結果的にどのイベントも中途半端な集客に終わってしまうリスクがある。実際、音楽系のイベントでは明らかに観客の分散が起きていた。
イベント主催者の立場から考えても、これだけ競合が多い状況では、それぞれが集客に苦戦することは容易に想像できる。特に中小規模のイベントは、大手エンターテイメントとの差別化が困難になっている。
札幌市としても、この状況を放置していいのだろうか。イベントの「量」を追求するだけでなく、「質」と「集中」を意識した戦略的な調整が必要な時期に来ているように感じた。
札幌がイベント開催に積極的な理由は、観光振興と地域経済活性化にある。特に夏季は観光のハイシーズンであり、短期間で最大限の経済効果を狙う必要がある。
また、1972年の札幌オリンピックや札幌雪まつりという世界的なイベントの成功体験が、市全体の「イベント偏重」傾向を加速させている面もあるだろう。雪まつりの経済効果は年間数百億円規模とされており、これが札幌市の基幹産業の一つになっている。
しかし、夏のイベントで同規模の効果を期待するのは現実的ではない。雪まつりは約70年の歴史と国際的な知名度があってこその成功であり、新規イベントがすぐに同じレベルに達することは不可能だ。
この日回った中で、明らかに成功していたイベントには共通点があった。
第一に、「明確なターゲット設定」だ。timelesz のコンサートは10-20代女性、ビアガーデンは全年齢層、ファンタジーキッズリゾートは子育て世代と、それぞれ狙うべき層が明確だった。
第二に、「アクセスの良さ」だ。成功しているイベントはすべて地下鉄駅から徒歩圏内か、専用の交通手段が用意されていた。
第三に、「話題性」だ。timelesz の独立後初ツアーや、相国寺展の国宝展示など、「今しか見られない」という特別感があった。
逆に苦戦していたイベントは、これらの要素が欠けていることが多かった。
最後に、肝心の札幌市民の反応はどうだったのか。
駅前で何人かの市民に話を聞いてみたが、反応は意外にも冷静だった。「毎週何かしらやってるから、特に珍しくない」「むしろ観光客が多くて、普段の生活に影響が出る」といった声も聞かれた。
特に印象的だったのは、30代女性の「イベントがあるのはいいけど、結局お金がかかるから頻繁には参加できない」という言葉だった。コンサートチケットは数千円から1万円超、家族でイベントに参加すれば軽く1万円は飛んでいく。
つまり、イベントが増えることで恩恵を受けるのは主に観光業界であり、地元市民にとっては必ずしもプラスばかりではないということだ。
この記事を読んで分かったことと考えるべきこと
札幌の7月19日を実際に回って分かったのは、「イベント大国」としての札幌の光と影だった。確かに選択肢は豊富で、経済効果も無視できない規模がある。しかし、量を重視するあまり質の向上や効率的な配置が後回しになっているという課題も見えてきた。
特に考えるべきは、「誰のためのイベントなのか」という根本的な問題だ。観光客誘致と地域経済活性化は重要だが、そこに住む市民の生活の質向上も同じく重要なはずだ。
札幌が真の「文化都市」「観光都市」として発展していくためには、イベントの戦略的な見直しが必要な時期に来ている。量から質へ、分散から集中へ──そんな転換期にある札幌の未来を、私たちは注視していく必要があるだろう。
イベント取材の合間に立ち寄った札幌の雑貨店で、思いがけない発見があった。北海道の人気者・シマエナガをモチーフにした切り絵御朱印が、夏祭りをテーマにデザインされていたのだ。
夏の夜、ほおずき提灯に照らされるシマエナガたち。この切り絵御朱印、細部まで愛らしさが詰まってて、思わずじっと見入ってしまう。透明感あるブルーも涼しげで、飾っておきたくなる一枚です。札幌の夏イベントの記念に、こんな北海道らしいアイテムを手に取るのも素敵かもしれない。
PR
▶ シマエナガの夏祭り、ちらっと見る 🔗 https://amzn.to/4eSWkuU
イベント情報
さっぽろ夏まつり関連
美術館・展覧会
札幌市観光情報
この記事は2025年7月19日に札幌市内で実際に取材を行った内容をもとに執筆しました。各イベントの詳細や最新情報については、上記の公式サイトをご確認ください。
筆:miku
ルポライター・みく
7月17日の「道みんの日」。北海道内の文化施設が無料開放されるという、年に一度の大イベントに私は足を運んだ。結論から言うと、この制度は確実に市民の文化的体験を広げているが、運営面での課題も浮き彫りになった一日だった。
朝9時、私は北海道博物館の前に立った。開館30分前だというのに、すでに20人ほどの列ができている。隣に並んだ70代の男性は「毎年楽しみにしているんだ」と話してくれた。過去の道みんの日では来場者数が通常の3倍以上に増加するという報告もある。この数字が示すのは、料金という障壁がいかに大きいかということだ。
館内に入ると、普段は静かな展示室に家族連れの声が響いていた。特に印象的だったのは、アイヌ文化の展示コーナーで熱心にメモを取る中学生の姿。「学校の課題で来たけど、思った以上に面白い」と彼女は話す。入館料570円が無料になることで、こうした学習機会が生まれているのは確かだ。
しかし、課題もある。午後2時頃に訪れた札幌市時計台は、入場制限がかかっていた。係員によると「普段の5倍以上の来場者で、建物の安全性を考慮して制限している」とのこと。明治時代の木造建築という制約の中で、どこまで多くの人を受け入れられるかは深刻な問題だ。
チカホ(札幌駅前通地下広場)では、健康インソールの体験販売会が開催されていた。地下広場の憩いの空間には多くの人が足を止めており、道みんの日に合わせたイベントとして注目を集めていた。この日は単なる無料開放日ではなく、道民の文化的結束を深める装置として機能している。
夕方、私は豊平館を訪れた。明治政府の迎賓館として建てられたこの建物は、普段は大人350円の入館料がかかる。しかし無料開放日だからこそ、普通の市民が気軽に足を運べる。「歴史的建造物を維持するには費用がかかる。でも、こうした機会がないと市民との距離が開いてしまう」と学芸員は複雑な表情を見せた。
北海道立近代美術館では、常設展が無料開放されていた。普段は一般510円の展示を、多くの家族連れが楽しんでいる。美術館の入場者データを見ると、道みんの日の来場者の約4割が「初回来館者」だという報告もある。つまり、この日をきっかけに新たな美術ファンが生まれている可能性がある。
ただし、すべてが順調というわけではない。もいわ山ロープウェイでは、通常の2倍の待ち時間が発生していた。夜景を楽しみに来た観光客からは「こんなに混むなら別の日にすればよかった」という声も聞かれた。
この日の体験を通じて気づいたのは、文化施設の「敷居の高さ」という問題だ。札幌市の各種調査では、市民の多くが「文化施設を利用したことがない」と回答している。料金の問題もあるが、それ以上に「何をしているのかわからない」「自分には関係ない」という心理的な壁が大きいのではないか。
道みんの日は、確実にその壁を低くしている。しかし問題は、この日だけの「お祭り」で終わってしまうことだ。本来なら、この日をきっかけに継続的な文化施設利用につながることが理想的だろう。
夜、札幌文化芸術劇場hitaruで開催されたコロッケのものまねショーは、昼の部14:30開演、夜の部18:30開演の2回公演で行われた。道みんの日に合わせた文化イベントとして、多くの市民が楽しんでいた。「無料の日だからこそ、こういう機会に触れられる」と話す観客の言葉が印象的だった。エンターテインメントも文化の一部であり、経済的な制約で諦めている人がいかに多いかを物語っている。
一方で、注目されていたZepp Sapporoでのclaquepot×工藤大輝ライブは、実際には7月17日19:00開演で開催されることが確認できた。Da-iCEの工藤大輝が「双子の兄」という設定のclaquepotとのツーマンライブツアーの一環で、札幌公演が道みんの日と重なったのは偶然だったようだ。
夜10時過ぎ、私の道みんの日体験は終わった。一日で複数の施設を回り、数十人の市民と話した結果、見えてきたのは北海道の文化政策の可能性と限界だった。
道みんの日は確実に市民の文化体験を広げているが、年に一度の「イベント」で終わらせてはいけない。重要なのは、この日をきっかけに生まれた文化への関心を、いかに継続的な利用につなげるかだ。
施設側は混雑対策と安全確保が急務であり、利用者側は「文化は特別なもの」という固定観念を捨てる必要がある。そして行政は、単なる無料開放ではなく、市民の文化的素養を向上させる長期的な戦略を描くべきだ。
2025年のデフリンピック開催を控え、北海道の文化的多様性を世界に発信する機会が近づいている。道みんの日で感じた市民の文化への潜在的な関心を、どう育てていくか。それが今後の北海道の文化政策の鍵となるだろう。
【修正点について】
【参考資料・公式リンク】
こんにちは、佐々木優です。私がIT企業を起業してから8年が経ちました。この間、日本のデジタル社会は目まぐるしく変化し、特に2025年に入ってからその変化は加速度を増している、というのが現場にいる私の実感です。
今日は、これから社会に出る皆さんに向けて、今のデジタル社会で実際に何が起きているのか、そしてこれからどう変わっていくのかをお話ししたいと思います。統計や白書に書かれていることももちろん大切ですが、それ以上に現場で感じている生の情報をお伝えできればと思っています。
正直に言うと、AIの進化スピードには私自身も驚いています。2022年にChatGPTが話題になった時、「これは面白いツールだな」程度に思っていたんです。でも2025年の今、状況は全く違います。
先日、Googleの「NotebookLM」を実際に使ってみたのですが、これには本当に驚かされました。2025年6月4日にノートブックをパブリックリンクとして誰とでも共有できる新機能が提供開始され、そして7月14日にはThe EconomistやThe Atlanticといった有名メディアと連携した「Featured Notebooks(おすすめのノートブック)」という厳選されたノートブック集が公開されるようになりました。この機能によって、信頼性の高い専門的な情報にAIを通じてアクセスできるようになったんです。
私の会社でも、昨年から生成AIの活用を本格的に始めています。最初は「効率化のツール」として考えていたのですが、今では業務の進め方そのものが変わってきています。単純な作業の自動化だけでなく、アイデア出しや企画書の初期案作成、さらには顧客とのコミュニケーションまで、AIが支援してくれる範囲がどんどん広がっているんです。
LINEヤフーが2025年7月14日に全従業員約11,000人を対象に業務における生成AI活用の義務化を前提とした新しい働き方を開始すると発表し、3年間で業務生産性を2倍にするという目標を掲げたニュースを見た時、「ついにここまで来たか」と思いました。私たちのような中小企業でも、もう「AIを使うか使わないか」ではなく、「どう使いこなすか」の段階に入っているということです。
LINEヤフーの取り組みで特に注目したのは、従業員の業務の3割を占める「調査・検索」「資料作成」「会議」という共通領域から着手している点です。これって、どの会社でも共通する課題なんですよね。「まずはAIに聞く」を基本原則として、ゼロベースの資料作成を禁止し、必ずAIでアウトラインを作成してから始めるルールを設けているそうです。
特に興味深いのは、大規模なLLM(大規模言語モデル)だけでなく、Microsoftの「Phi」シリーズのような小規模なモデルも注目を集めていることです。140億パラメータの「Phi-4」は、複雑な推論に対応しながらも軽量で高速処理が可能。これって、私たちのような企業にとってはすごく実用的なんです。
なぜかというと、巨大なモデルを使うにはコストがかかりすぎるし、社内の機密情報を外部のサービスに送るのは不安だからです。でも小規模なモデルなら、社内のサーバーで動かせるし、コストも抑えられる。実際、私たちもローカル環境で動く小規模モデルの導入を検討しているところです。
NTTグループがLLMの追加学習なしで決められた長さ以上のテキストを生成できる技術を開発したというニュースも、現場目線では非常に重要です。学習コストの削減って、私たちのような企業にとっては死活問題なんです。
私が起業した当時、最新技術を使おうと思ったら、とにかくお金がかかりました。でも今は、効率的な技術開発によってコストが下がり、中小企業でも最先端の技術を活用できるようになってきています。これは本当にありがたいことです。
Web3の分野では、従来のように大企業が巨額の資金を投じてコンテンツを作る時代から、個人クリエイターが小さく始めて大きく育てる時代に変わってきています。
私の知り合いにも、NFTアートで収益を上げているクリエイターがいます。彼らの話を聞いていると、技術的なハードルが下がったことで、アイデアさえあれば誰でもチャレンジできる環境が整ってきていることを実感します。
特にYahoo!きっずの「AIでゲームつくりエイター」サービスは、子どもたちにとって素晴らしい学習機会だと思います。2025年7月11日にサービス開始されたこの取り組みでは、生成AIを活用した5種類のゲームを通して、プロンプトの書き方や設計方法を楽しく学べます。私が子どもの頃は、プログラミングといえば専門的で難しいものでした。でも今の子どもたちは、AIを使いながら自然にゲーム制作を学べる。これは本当にうらやましいです。
富士通と理化学研究所が2025年4月22日に256量子ビットの超伝導量子コンピューターを開発したニュースは、IT業界にいる私たちにとって本当にエキサイティングな出来事でした。量子ビットの集積化、極低温状態を保つ熱設計、高密度実装…これらの技術的課題を日本の研究機関が克服したということは、我が国の技術力の高さを示していると思います。
私は大学時代に量子力学を少し勉強しましたが、正直言ってとても難しくて「こんなものが実用化されるのはずっと先の話だろう」と思っていました。でも2025年になって、HPCとの融合による実用化が現実味を帯びてきています。
この256量子ビットマシンは、外部ユーザーに提供されている超伝導量子コンピューターとしては世界最大級で、2025年度第一四半期中に企業や研究機関に向けて提供が開始される予定です。3次元接続構造により、64量子ビット機から容易に大規模化できることも実証されました。
ただし、量子コンピューターの実用化は、サイバーセキュリティの観点では大きな課題でもあります。現在の暗号技術が危殆化する可能性があるからです。総務省が量子暗号通信技術の研究開発を2025年度から本格的に推進しているのも、この危機感の表れだと思います。
私たちのような企業も、将来的には量子暗号に対応したセキュリティシステムへの移行を考えなければならないでしょう。技術的な詳細はまだ完全に理解できていませんが、盗聴を確実に検知できる量子の物理的特性を活用した技術というのは、本当に革新的だと思います。
サイバー攻撃について話すと、「自分の会社は大丈夫」と思われる方もいるかもしれません。でも実際には、規模に関係なくどの企業も標的になり得るのが現実です。
私の会社でも、昨年だけで複数回、怪しいメールや不審なアクセスを確認しました。幸い大きな被害はありませんでしたが、常に緊張感を持って対策を講じています。情報通信研究機構(NICT)の観測では、IoT機器を狙った攻撃が全体の約3割を占めているという報告もあります。
特に気になるのは、2025年の大阪・関西万博前後にサイバー攻撃が増加する可能性が指摘されていることです。関西の中小企業が狙われる懸念もあり、私たちも他人事ではありません。
2025年5月16日に「能動的サイバー防御法案」が参院本会議で可決・成立し、同年5月23日に公布されたことは、企業経営者として非常に心強く感じています。国や重要インフラの安全確保に向けた政府の本気度が伝わってきます。
この法律により、国による通信監視や官民の情報共有で攻撃の予兆をつかみ、警察と自衛隊が無害化する措置を取れる体制が構築されます。基幹インフラ事業者には報告義務も課せられることになりました。
ただし、法律ができたからといって、企業側の責任が軽くなるわけではありません。むしろ、これまで以上にセキュリティ対策への取り組みが求められるようになると考えています。
情報処理推進機構(IPA)の「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、私たちのような中小企業にとって本当にありがたい存在です。ワンパッケージで安価にセキュリティ対策を提供してくれるので、限られた予算の中でも適切な対策を講じることができます。
実際に相談窓口を利用したこともありますが、専門的なアドバイスを分かりやすく説明してもらえました。Oracle JavaやMicrosoft製品の脆弱性情報も定期的に更新されているので、常にチェックするようにしています。
これは本当に深刻な問題です。私の会社でも、セキュリティに詳しいエンジニアを採用しようとしていますが、なかなか見つからないのが現実です。技術の進歩に比べて、それを理解し適切に運用できる人材の育成が追いついていません。
総務省がNICT(情報通信研究機構)を通じて「CYDER」(実践的サイバー防御演習)や「SecHack365」といった育成プログラムを推進していることは素晴らしいと思います。でも、それでもまだ圧倒的に人材が不足している状況です。
新社会人の皆さんには、ぜひセキュリティ分野にも興味を持ってもらいたいです。技術的に挑戦的で、社会的意義も高く、需要も非常に大きい分野です。
マイナンバーカードの普及率が2025年2月末時点で78.0%(約9,700万枚)に達したというニュースを見た時、「ようやくここまで来たか」という感慨がありました。私自身、確定申告でe-Taxを使っていますが、紙の書類で手続きしていた頃と比べると、本当に楽になりました。
法人税申告の86.2%、所得税申告の69.3%がe-Taxを利用しているという数字も、デジタル化の浸透を示していると思います。ただし、まだ完全にペーパーレスになったわけではなく、一部の手続きでは依然として紙の書類が必要な場合もあります。
北海道帯広市のスマート農業の実証事業には、大きな可能性を感じています。2024年度に「帯広市川西農業協同組合(JA帯広かわにし)」が中心となって総務省「令和6年度地域デジタル基盤活用推進事業」の実証事業を活用し、ドローンとAIを組み合わせて作物を管理したり、複数の無人トラクターを同時に動かしたりする実証試験が行われました。人手不足が深刻な農業分野でのデジタル活用は、まさに課題解決の好例だと思います。
私の実家も地方にあるのですが、高齢化が進んで農業の担い手が減っているのを目の当たりにしています。こうした技術が普及すれば、少ない人数でも効率的に農業を続けられるようになるかもしれません。
京都府京丹波町の「京丹波GREEN Pay」のようなデジタル地域通貨も興味深い取り組みです。地域経済の活性化にデジタル技術を活用するという発想は、多くの地方自治体が参考にできると思います。
2024年1月の能登半島地震での教訓を受けた放送ネットワークの強靱化支援は、非常に重要な取り組みだと感じています。災害時にテレビ放送が重要な情報源になることは、私自身も東日本大震災の時に痛感しました。
携帯電話基地局の停電対策強化、移動基地局、無人航空機、低軌道衛星等の活用拡充など、通信ネットワークの強靱化も進んでいます。私たちのようなIT企業も、BCP(事業継続計画)の一環として、これらの動向をしっかりと把握しておく必要があります。
これは私自身の経験からも言えることですが、エンジニアの働き方に関する調査結果は、現場の実感とよく合っています。「ハイブリッド型勤務」が半数以上、「フルリモート勤務」が約3割という数字は、私の周りのエンジニアの状況ともほぼ一致しています。
私の会社でも、コロナ禍をきっかけにリモートワークを導入しましたが、今ではそれが当たり前になっています。フルリモート勤務の満足度が9割以上という調査結果も納得できます。実際、リモートワークによって通勤時間がなくなり、集中して作業できる環境を整えやすくなったというメンバーが多いです。
フルリモートから出社義務化を経験したエンジニアの約7割が受け身の姿勢を示し、約2割は仕事を続けられないと感じるという調査結果には、正直驚きました。でも、実際に私の知り合いのエンジニアからも似たような話を聞くことがあります。
出社に抵抗を感じる理由として「通勤が負担になる(46.7%)」「リモート勤務の方が生産性が高い/集中できる(45.0%)」「ワークライフバランスが悪化する(35.2%)」が挙げられていますが、これらは本当にその通りだと思います。
私自身、創業当初は「みんなで同じオフィスにいることで一体感が生まれる」と考えていました。でも実際にリモートワークを経験してみると、必ずしもそうではないことが分かりました。大切なのは、働く場所ではなく、いかに効率的に成果を出すかということです。
エンジニアが出社を受け入れられる条件として「出社日が柔軟に選べる(ハイブリッド型勤務)」が49.3%で最も多いという結果は、現場の感覚とも合っています。私の会社でも、完全にリモートにするのではなく、必要に応じて出社できるハイブリッド型を採用しています。
「出社は短期・一時的」(39.5%)、「勤務時間の自由度(フレックスタイム制や短時間勤務など)」(36.7%)という条件も理解できます。プロジェクトの状況やチームの連携が必要な時だけ出社して、普段は各自が最も生産性の高い環境で働く。これが理想的な働き方だと思います。
世界のパブリッククラウドサービスの売上高が2024年に7,733億ドルに増加したという数字を見ると、この市場の巨大さと成長力を改めて実感します。Amazon、Microsoft、Googleが大きなシェアを占めているのは、私たちのような企業でも実感するところです。
私の会社でも、これらのクラウドサービスを活用していますが、その便利さと同時に、海外事業者への依存という課題も感じています。データの保存場所や管理方法について、経営判断として慎重に検討する必要があります。
国内のAIOps/運用自動化市場が2024年度に20%弱の成長を見込んでいるという予測は、運用効率化への需要の高まりを示していると思います。私たちのような中小企業でも、人手不足を補うために自動化への投資を検討しています。
ただし、日本のデジタル分野の国際競争力が低いという課題は深刻です。デジタル関連サービスの国際収支の赤字拡大は、国全体として取り組むべき問題だと感じています。
「ITreview Grid Award 2025 Summer」で約1,230製品・サービスが評価されたというニュースは、IT選定の参考になります。私たちが新しいツールやサービスを導入する際も、実際のユーザーレビューを重視しています。
特にB2B向けのIT製品は、実際に使ってみないと分からない部分が多いです。ユーザーのリアルな声が集約されているプラットフォームは、本当に価値があると思います。
NTTグループの取り組みを見ていると、単なる通信事業者を超えて、社会課題解決に幅広く貢献していることが分かります。
新潟大学との遠隔触診技術の共同研究は、医師不足・偏在という地域課題の解決に直結する取り組みです。私の実家がある地方でも、専門医不足は深刻な問題になっています。こうした技術が実用化されれば、多くの人が助かると思います。
鋼材を使用したインフラ施設の画像から腐食の進行を予測する技術も、保全コスト削減に大きく貢献するでしょう。日本のインフラの老朽化は深刻な問題ですから、AIを活用した効率的な保守管理は必要不可欠です。
生物多様性ビッグデータを運営する株式会社バイオームへの出資や、衛星画像データによる植生および生物の広域推定技術の開発など、環境分野への取り組みも印象的です。企業活動と環境保護の両立は、これからの時代に不可欠な視点だと思います。
NTTパビリオンの取り組みや、「つながるっ展」のようなイベントを見ていると、万博への期待が高まります。私も実際に万博会場を訪れる予定ですが、最新のデジタル技術が一堂に会する貴重な機会だと思っています。
万博は単なるイベントではなく、日本の技術力を世界に示すチャンスでもあります。特にデジタル分野での競争力向上のきっかけになればと期待しています。
これまで長々とお話ししてきましたが、新社会人の皆さんに伝えたいことは、「変化を恐れずに、積極的に新しい技術に触れてほしい」ということです。
私が社会人になった頃と比べて、今は本当に多くの可能性が開かれています。AIや量子コンピューター、Web3など、SF映画の中でしか見たことがなかった技術が現実のものになっています。
一方で、サイバーセキュリティのような課題も深刻化しています。でも、これらの課題があるからこそ、皆さんのような若い世代の力が必要なんです。
2025年のデジタル社会は、まさに激動の時代です。AI、量子コンピューター、Web3といった技術革新がある一方で、サイバーセキュリティや人材不足といった課題もあります。
でも、こうした変化の時代だからこそ、新しいアイデアや若い力が求められています。皆さんには、既成概念にとらわれることなく、自由な発想でこの変化に立ち向かってほしいと思います。
私自身、まだまだ学ぶことがたくさんありますが、これからも現場の視点を大切にしながら、日本のデジタル社会の発展に貢献していきたいと考えています。
新社会人の皆さんの活躍を心から応援しています。一緒にこの変化の波を乗り越えて、より良いデジタル社会を築いていきましょう。
本記事は現在入手可能な公開情報に基づいて作成されており、各種データや事実については上記の信頼できる情報源から引用しています。技術の進歩は日々続いているため、最新の情報については各公式サイトをご確認ください。
雨が降る水曜日の札幌で、私は何かが終わろうとしていることを感じていた。さっぽろ羊ヶ丘展望台のラベンダー刈り取り体験が、2025年7月16日をもって終了する。たった13日間の短いイベントだったが、この街の人々にとって特別な意味を持っていたことを、私は現地で目の当たりにした。
この記事を読んでわかること
札幌市民の日常に根ざしたイベントの実態
雨天時における地域コミュニティの対応力
観光地化が進む中での「本当の札幌らしさ」とは何か
札幌市の子育て支援制度の現状と課題
7月上旬、私は羊ヶ丘展望台を訪れた。1,200平方メートルの畑に1,000株のラベンダーが咲いている光景は確かに美しかったが、正直に言うと「これが札幌の夏の名物?」と疑問に思った。富良野のラベンダー畑を知っている人なら、規模の違いは歴然だ。
しかし、ハサミを手に取って実際にラベンダーを刈り取ってみると、その理由が分かった。ここは観光地としての「見せ物」ではない。札幌市民の夏の思い出を作る場所なのだ。隣で作業していた60代の女性は「毎年来てるの。家に持って帰って、孫と一緒にポプリ作るのが楽しみで」と話してくれた。
札幌市民なら免許証を見せるだけで大人500円、子ども無料で入場できる。この制度、実は札幌市内の他の施設でも見られる特徴で、市民に対する配慮の現れだと私は考えている。観光都市として発展する一方で、地元住民を大切にする姿勢がまだ残っているのだ。
7月16日の天気予報を見て、私は正直がっかりした。午前中の降水確率は60~70%。せっかくのラベンダー最終日が雨になるなんて。でも、取材を進めるうちに、札幌の「雨の日の過ごし方」の豊富さに驚かされることになった。
チ・カ・ホ(札幌駅前通地下広場)では、相続・終活サポートフェアが開催されている。一見地味なイベントだが、高齢化が進む札幌にとって切実な問題だ。実際、北海道の高齢化率は32.2%(2020年国勢調査)で、全国平均の28.9%を大きく上回っている。こうしたイベントは決して「ついで」ではなく、市民にとって必要なサービスなのだ。
札幌市民交流プラザでの「人間関係で分かり合えない苦しみ」をテーマにしたセミナーも興味深い。参加費1,000円という手頃な価格設定からも、多くの人に門戸を開こうという意図が感じられる。コロナ禍以降、人間関係に悩む人が増えているという話もよく聞く。こういう場所があることを、もっと多くの人に知ってもらいたい。
取材中に偶然知ったのが「札幌市ファミリー・サポート・センター事業」だ。これ、正直すごいシステムだと思う。
| 利用時間帯 | 料金(30分あたり・一人目) |
|---|---|
| 月~金 7:00~19:00 | 350円 |
| 土日祝・年末年始・上記時間外 | 400円 |
※二人目以降は割引あり
30分350円で子どもを預けられるって、都市部の民間サービスと比べると破格だ。東京なら同じようなサービスで1時間2,000円以上することもザラにある。
ただし、利用するには事前登録が必要で、説明会は月2回(第2・4土曜日)のみ。働く親にとって土曜日の説明会参加はハードルが高いのではないかと感じた。制度は良いが、利用しやすさに課題があるように思える。
私が注目したのは「親のリフレッシュ」も利用理由として認められている点だ。「仕事以外で子どもを預けるなんて」という価値観がまだ根強い中、こうした配慮は画期的だと思う。
7月下旬から8月にかけて札幌市東区で開催される夏祭りのラインナップを見ていて気づいたことがある。
これらはどれも小規模で、観光客向けというより完全に地域住民のためのイベントだ。私は昨年、苗穂連町夏祭りを取材したことがあるが、フラワーオークションで300円で花束が買えたり、地元商店街の手作り感満載の出店があったりと、決して華やかではないが温かみのある祭りだった。
こういうイベントが同じ地区で複数開催されるのは、地域コミュニティがしっかり機能している証拠だと私は考えている。人口約197万人の政令指定都市でありながら、まだこうした「町内会レベル」のつながりが生きているのは、札幌の大きな特徴だ。
札幌芸術の森美術館で開催中の「小松美羽 祈り 宿る Sacred Nexus」展の音声ガイドをGLAYのTERUが担当していることを知って、正直びっくりした。小松美羽は現在アートマーケットで注目される現代アーティストの一人で、作品によっては数百万円の値がつくこともある。
一方で、北海道立近代美術館では「1945-2025 美術は何を記憶しているか」という重厚なテーマの展示が開催される。戦後80年を迎える2025年という節目を意識した企画だろう。
この2つの展示の温度差を見ていると、札幌の文化シーンの複雑さを感じる。商業的な成功を狙ったポップなイベントと、社会的メッセージ性の強い硬派な展示が同時期に開催されている。どちらも必要だが、果たして若い世代はどちらに足を向けるのだろうか。
「雨のちくもり」「最高気温30℃」という7月16日の予報を見て思ったのは、札幌の人たちの天気に対する向き合い方の上手さだ。
雨が降れば地下街のイベントを楽しみ、晴れれば羊ヶ丘でラベンダーを刈る。当たり前のことかもしれないが、この切り替えの早さは、冬の厳しさを知っている札幌ならではの知恵だと思う。
私は関東出身だが、雨の日に「今日は外出をやめよう」と考えがちだ。でも札幌では雨の日でも楽しめる選択肢がこれだけ用意されている。これは単なる行政サービスではなく、この街で暮らす人たちの生活の知恵が形になったものなのだろう。
取材を通して見えてきたのは、観光都市として成長する札幌と、地域コミュニティを大切にする札幌の二面性だ。ラベンダー刈り取り体験のような小さなイベントに、市民が家族で参加している光景は微笑ましい。一方で、初音ミクのアジアツアーのような世界規模のプロジェクトが札幌発で生まれていることも事実だ。
この街が抱える課題も見えてきた。子育て支援制度の充実度は高いが、利用のハードルがやや高い。文化イベントは多様だが、若い世代との距離感に課題がある。地域の祭りは活発だが、担い手の高齢化は進んでいるだろう。
でも、だからこそ札幌は面白い街だと私は思う。完璧ではないが、住む人のことを考えた街づくりをしようとする意志が随所に感じられる。7月16日の雨の日に、この街のことを少し深く知ることができて良かった。
この記事を読んで分かったことと考えるべきこと
札幌は観光都市と地域コミュニティの二面性を持つ街である
市民向けサービスは充実しているが、利用しやすさに改善の余地がある
天候に左右されない文化・コミュニティ活動の多様性が札幌の強み
地域の祭りや小規模イベントが、大都市でありながら人と人のつながりを維持している
今後は制度の充実度だけでなく、アクセスしやすさを重視した街づくりが求められる
(ルポライター・みく)
こんにちは。IT企業を経営している佐々木優です。
今日は珍しく、プライベートな話から始めさせてください。先週末、大学時代の友人と久しぶりに会ったとき、「最近のAIアプリってどうなの?特にiPhoneで使えるやつ」って聞かれたんです。
「AIなら仕事で散々触ってるよ」と答えたものの、エンターテイメント系のAIアプリって実は全然知らなくて。ちょっと恥ずかしかったですね。それで帰宅後、App Storeでいろいろ探してみることにしました。
そこで出会ったのが「Grok」でした。イーロン・マスクが関わってるAIということは知っていたけれど、スマホアプリがあることは知りませんでした。
正直に言うと、最初はかなり期待していました。「さすがイーロン・マスク、きっとすごいものを作ってるんだろう」って。
でも実際にダウンロードして使ってみると…うーん、思っていたのと違うというか。
まず、よく噂で聞いていた「3Dキャラクターとの対話」みたいな機能は見当たりませんでした。私が使っているiPhone 14 Proが古いのかと思って調べてみたんですが、そもそもそういう機能自体がないみたいで。
どこかで「コンパニオンモード」という名前を聞いたような気がしていたんですが、勘違いだったようです。人の記憶って曖昧ですね。
それでも、せっかくダウンロードしたので一週間ほど使ってみました。
基本的にはテキストベースのチャットボットという感じで、ChatGPTやBardと似たような使用感です。ただ、回答の傾向が少し違うかな。もう少しフランクというか、砕けた感じの返答が多い印象でした。
私が試したのは主に以下のような用途:
意外だったのは、雑談の相手としては結構良かったことです。仕事のストレスとか、今後の事業展開についてとか、なんとなく話し相手が欲しいときに使っていました。
「今日は会議が多くて疲れました」って入力すると、「お疲れ様です。会議続きは本当に大変ですよね。何か気分転換になることはありますか?」みたいな返答が返ってきて、なんとなく気持ちが楽になったり。
ChatGPTだともう少し事務的な感じがするんですが、Grokはもう少し親しみやすい感じがしました。これは個人の感覚なので、人によって違うかもしれませんが。
一方で、情報の正確性については少し気になることがありました。特に最新の技術情報や市場データについて質問したとき、たまに古い情報や間違った情報が混じっていることがありました。
例えば、「2024年のAI市場規模」について聞いたときの回答が、明らかに2023年の古いデータを基にしているような感じでした。これは仕事で使うには少し不安ですね。
一週間使ってみた結論としては、「雑談相手としては良いけれど、仕事には使いにくい」という感じでした。
私みたいに普段からChatGPTやClaude、Bardなどを使い分けている人には、特に新鮮味はないかもしれません。でも、初めてAIチャットボットを使う人には良い入門編になるかも。
特に、以下のような人には向いているんじゃないかと思います:
無料でも基本的な機能は使えるので、まずは試してみる分には良いと思います。有料プランもあるようですが、現時点で私は無料版で十分かなと。
月額制のサブスクリプションサービスって、気づいたら結構な金額になってることありませんか?私も定期的に見直しをするんですが、「これ、本当に使ってる?」ってサービスが結構あったりして。
Grokについても、しばらく無料版で様子を見てから判断するのが良いかもしれません。
せっかくなので、普段私が使っている他のAIサービスとも比較してみました。
やっぱり安定感はこれが一番です。特に技術的な質問や複雑な文章作成には頼りになります。ただ、少し堅い感じがするのが玉にキズ。
私が最近よく使っているのがこれです。長文の処理が得意で、文章の推敲やレビューによく使っています。日本語の自然さも良い感じ。
Googleの検索と連携しているので、最新情報が必要なときに便利です。ただ、たまに的外れな回答をすることがあるのが気になります。
上記3つと比べると、まだ発展途上という印象です。ただ、親しみやすさという点では他にない特徴があるかも。
率直に言うと、現時点でのGrokは「特別すごい」というほどではありませんでした。でも、これは別に悪いことではないと思います。
私が初めてiPhoneを手にしたのは2008年の3Gでしたが、当時は「電話とメールとネットができる程度」でした。それが今では私たちの生活に欠かせないツールになっています。
AIも同じで、今はまだ発展途上ですが、数年後には私たちの想像を超える進化を遂げているかもしれません。
私の会社では、AI技術を活用したサービス開発も手がけています。その立場から見ると、現在のAI技術の進歩は本当に目覚ましいものがあります。
ただし、同時に限界も見えてきているのも事実です。特に、情報の正確性や、文脈の理解、そして何より「人間らしさ」という部分では、まだまだ改善の余地があります。
Grokについても、今後のアップデートで大きく改善される可能性があります。イーロン・マスクという人は、良くも悪くも「やりすぎる」傾向があるので、予想外の展開があるかもしれませんね。
長々と書きましたが、結論としては「とりあえず無料で試してみる分には損はない」という感じです。
私自身も、今後もしばらく使い続けてみようと思っています。特に、他のAIサービスとの使い分けという観点で、何か新しい発見があるかもしれません。
ただし、期待値は適度に抑えておいた方が良いかも。「革命的な体験」を期待すると、少しがっかりするかもしれません。
この記事を書きながら思ったのは、AIの進歩って本当に早いということです。2年前には考えられなかったことが、今では当たり前になっています。
私たちIT業界で働く人間は、常に新しい技術にキャッチアップしていく必要があります。時には失敗することもあるし、期待外れのこともある。でも、それも含めて技術の進歩に貢献できているのかなと思います。
Grokも、今はまだ発展途上かもしれませんが、将来的には私たちの仕事や生活を大きく変える存在になるかもしれません。そんな可能性を感じながら、今後も新しい技術に触れ続けていきたいと思います。
佐々木優
2024年7月15日 記
追記: この記事は私の個人的な体験と感想に基づいています。技術の進歩は日進月歩なので、読まれる時期によっては状況が変わっている可能性があります。また、使用感については個人差があることをご理解ください。
…なんて、偉そうに始めてみたけど、正直に言うわね。今、この文章を書いているのは深夜の2時。サーバーがどうとか、クライアントの無理難題がどうとか、そういう日々の喧騒からやっと解放された時間。こんな時間に私が何を考えてるかというと、「あー、もう全部放り出して温泉にでも行きたい」ってこと。
笑えるでしょ?IT企業の社長なんて聞こえはいいけど、現実はこんなもん。キラキラした世界じゃない。泥臭くて、地味で、理不尽なことで腹が立つ毎日。君たちがこれから飛び込む世界も、たぶん、そんなに変わらない。
でもね、年に一回だけ、このどうしようもなく面倒なIT業界が、最高に愛おしく思える日があるの。それが『Cloud Operator Days Tokyo』、私たちがCODTって呼んでる、あのお祭りの日。
今日は、その話をさせて。教科書にも、会社の研修資料にも載ってない、私の本音の話。
いきなりごめんなさい。でも、本当なの。なんか馴れ合いみたいで、意識高い人たちの集まりみたいで、ちょっと苦手だった。私が若かった頃は、技術は一人で盗んで、磨くものだと思ってたから。
でも、会社を立ち上げて、一人じゃどうにもならない壁に何度もぶつかって…。そんな時、藁にもすがる思いで参加したのが、数年前のCODTだった。
会場に入って驚いた。スーツ姿なんてほとんどいない。みんな、普段着で、そこら中でPCを開いて何か作業してたり、知らない人同士で「あの件、結局どうなりました?」「いやー、それがダメで…」なんて、まるで昨日の続きみたいな会話をしてる。
登壇者も、流暢なプレゼンなんてしない。緊張で声が震えてたり、資料がうまく映らなかったり。でも、語られる言葉には、嘘がなかった。「この実装で3日徹夜しました」「上司を説得するのに半年かかりました」…そういう、生々しい体験談ばかり。
その時、ふっと力が抜けたの。「ああ、みんな同じなんだ」って。一人で戦ってる気になってたけど、日本中に、こんなにたくさんの仲間がいたんだって。私が嫌いだった「コミュニティ」は、馴れ合いの場所じゃなくて、傷だらけの戦士たちが束の間、鎧を脱いで傷を舐め合う、野戦病院みたいな場所だったのよ。
■データなんて、後からついてくるもの
よくイベントの価値を示すのに、参加者数とかセッション数の表が使われるでしょ。
| 年度 | 私の勝手な印象 |
| 2022 | まだまだ身内感。でも熱気はヤバかった。 |
| 2023 | 「あの人、Twitterで見たことある!」が増えてきた。 |
| 2024 | 若い子がすごく増えた。休憩時間の雑談が一番面白い。 |
| 2025 | もう、お祭り。カオス。でも、それがいい。 |
ほら、こんな感じ。公式の統計データ(もちろん、そういうのも大事よ)より、私にとってはこっちの肌感覚の方がずっとリアル。数字じゃなくて、「熱」なのよ、あそこにあるのは。
今年の目玉は「OpenStack15周年」らしいわね。正直、ピンとこないでしょ?「なんか昔流行ったやつ?」くらいの感覚かもしれない。
うちの会社でも、数年前にプライベートクラウドをOpenStackで組んだことがある。はっきり言って、地獄だったわ。ベンダーに丸投げできるような甘い世界じゃない。英語のドキュメントと格闘して、原因不明のエラーに頭を抱えて、夜中にデータセンターに駆け込んだことも一度や二度じゃない。
「なんでAWSじゃダメなんですか!」って、若いエンジニアに泣きつかれたこともあった。その通りよ。楽な道はいくらでもあった。でも、どうしても自分たちの手で、自分たちのインフラを完全にコントロールしたかった。あの時、もしOpenStackのコミュニティがなかったら、うちの会社は潰れてたかもしれない。
メーリングリストに拙い英語で質問を投げたら、会ったこともないブラジルのエンジニアが「それはたぶん、このパラメータが原因だぜ!」って返事をくれたり。国内の勉強会で「もう無理です…」って愚痴ったら、「うちもそこで3ヶ月ハマりましたよ」って笑いながら解決策を教えてくれる人がいたり。
だから、私にとってOpenStackは、ただの技術じゃない。あの時の苦しみと、助けてくれた人たちの顔がセットで思い出される、青春そのものみたいなものなの。15年続いた理由なんて、難しい理屈じゃない。そういう、人と人との繋がりがあったから。ただ、それだけなんだと思う。
CODTで語られる事例って、本当にひどいのよ(笑)。
| 事例の記憶 | 私の感想 |
| 中小企業の自動化改革 | 「自動化したはずが、余計に仕事が増えた話」から始まった。最高。 |
| AI予兆検知運用 | 日立さんみたいな大企業が「AI、最初は全然言うこと聞いてくれませんでした」って正直に話すのがすごい。 |
| OpenStack×エッジ | 「現場に設置したら、夏場の熱でサーバーが落ちた」みたいな話。他人事じゃない。 |
| コミュニティ連携事例 | 「引き継ぎ資料がなくて、退職した人に電話した」って話、うちもやったことある。 |
あるスタートアップの若い子が、「IaC(Infrastructure as Code)を導入して、何度もインフラを全部吹き飛ばしました」って、笑いながら話してたセッションが忘れられない。普通なら隠したいじゃない、そんな大失敗。でも、彼はそれを「一番の財産です」って言ったの。
失敗を隠さない。それを笑い飛ばして、みんなの教訓にする。なんて強いんだろうって、本気で感動した。キラキラした成功事例を100個聞くより、たった一つの、そういう生々しい失敗談の方が、よっぽど私たちの血肉になる。
誤解しないでほしいんだけど、AWS Summitとか、他の大きなイベントを否定する気は全くないの。最新情報をキャッチアップするために、私も参加するし、うちの社員にも行かせる。
でもね、家に帰るときの気持ちが、全然違うのよ。
大きなイベントの帰りは、「ああ、うちはまだまだだな」「あれもこれも勉強しなきゃ」って、少し焦る気持ちになることが多い。宿題をたくさん抱えて帰る感じ。
でも、CODTの帰りは、違う。なんていうか、飲み会で友達と語り明かした後のような、不思議な高揚感と安心感がある。「よし、明日からまた頑張るか!」って、自然に思える。
どっちが良いとか悪いとかじゃない。でも、もし君が今、仕事に少し疲れていたり、一人で悩んでいたりするなら、必要なのは新しい宿題じゃなくて、背中を叩いてくれる仲間なんじゃないかな。
毎日モニターを睨んで、キーボードを叩いて。ふと、「私、何のためにこんなことしてるんだっけ?」って思うこと、ない?
でもね、君が今見ているそのシステムは、どこかの会社の、誰かの生活を、確実に支えてる。自治体のサービスかもしれないし、病院の予約システムかもしれない。私たちが「運用」しているのは、社会の心臓なのよ。私たちが手を止めれば、社会のどこかで、誰かが必ず困る。
その責任は、ものすごく重い。でも、同じくらい、誇らしい仕事だと思わない?
CODTで話している人たちは、みんなそのことを知っている。自分の仕事が、ただの作業じゃなくて、社会に繋がっていることを、肌で感じている。だから、あんなに熱く語れるんだと思う。
長々と、私の自分語りに付き合ってくれてありがとう。
別に、「絶対にCODTに参加しろ!」なんて言うつもりはないわ。オンラインで動画を見るだけでもいい。Twitterでハッシュタグを追うだけでもいい。
でも、もし。もし、君が今の仕事に少しでも息苦しさを感じていたり、自分の未来が見えなくて不安になったりしているなら。一度でいいから、あのカオスな空間を覗いてみてほしい。
何か劇的に変わる保証なんてない。明日から急に仕事ができるようになるわけでもない。でも、一つだけ約束する。
「悩んでいるのは、自分だけじゃなかったんだ」
そう思えることだけは、私が保証する。
それって、明日からもう一日だけ頑張るための、十分な理由になるんじゃないかしら。
会場のどこかで、疲れた顔でコーヒーを飲んでる女がいたら、それは私かもしれないわね。その時は、気軽に声をかけてよ。
じゃあ、またどこかの現場で。
佐々木 優
こんにちは。札幌の週末情報をお届けしている当ブログから、新しい参加型企画のお知らせです。
街の空を見上げたとき、
駅のホームでふと立ち止まったとき、
通りすがりのポスターに足を止めたとき――
そんな「特別じゃないけど、ちょっと印象に残る札幌の金曜日」。
あなたの目線で撮った1枚を、ぜひ投稿してみませんか?
この企画では、札幌市内または近郊で撮影した
金曜日限定の写真を募集しています。
写真のジャンルは自由です。
「イベントに行ってなくてもいい」のがこの企画のポイント。
何気ない日常の札幌を、みんなで記録していきましょう。
📷 投稿方法は、以下の3ステップ!
💡 コメントも短くてOK!
「夕方の空がきれいでした」くらいの一言でも大丈夫です。
投稿いただいた写真の中から、
毎週1枚だけ、選ばれた写真を
当ブログの記事内や音声番組で紹介します!
また、選ばれた写真は記事のアイキャッチ画像やカバーにも採用される可能性があります。
あなたの1枚が、多くの人の目にふれるきっかけになるかもしれません。
✅ スマホでちょっと写真を撮るのが好きな方
✅ イベントには行かないけど札幌の街が好きな方
✅ SNSで発信したいけどネタに悩んでいる方
✅ 週末に“何か1つ記録したい”方
札幌の週末は、にぎやかなイベントやライブだけじゃありません。
小さな風景、静かな時間、人の気配――それらもまた、かけがえのない“札幌の金曜日”です。
この企画は、そうした日常の断片を
読者みんなで集めて、札幌という街の“今”を共有する試みです。
イベントに参加する人も、そうじゃない人も。
プロカメラマンも、スマホユーザーも。
誰もが参加できる、やさしい札幌のアーカイブ。
一緒につくっていきませんか?
ちょっとした風景も、
「#今日の札幌金曜」をつけて投稿するだけ。
「札幌の金曜日って、こんなに豊かなんだ」
そんな声が生まれる場を、みんなで作れたら嬉しいです。
あなたの“今週の1枚”、お待ちしています!
📢 投稿用ハッシュタグ:#今日の札幌金曜
📆 対象日:毎週金曜日に札幌で撮影された写真
#今日の札幌金曜 #札幌フォト #札幌日常 #札幌街歩き #金曜の風景 #スマホ写真 #参加型企画
みく(25歳・経理担当)のメンバー日記
今日は会社の新事務所(って言っても中古マンションの一室なんだけど)での撮影会でした。
何の撮影か?って??
私達、リミブレイクのLPに載せるスタッフ紹介ページに載せる写真なんです。
正直、最初は「またー?」って思ってたんですが、予想を遥かに超える一日になってしまって…。今のうちに記録しておかないと、絶対に忘れちゃいそうなので日記に残しておきます。
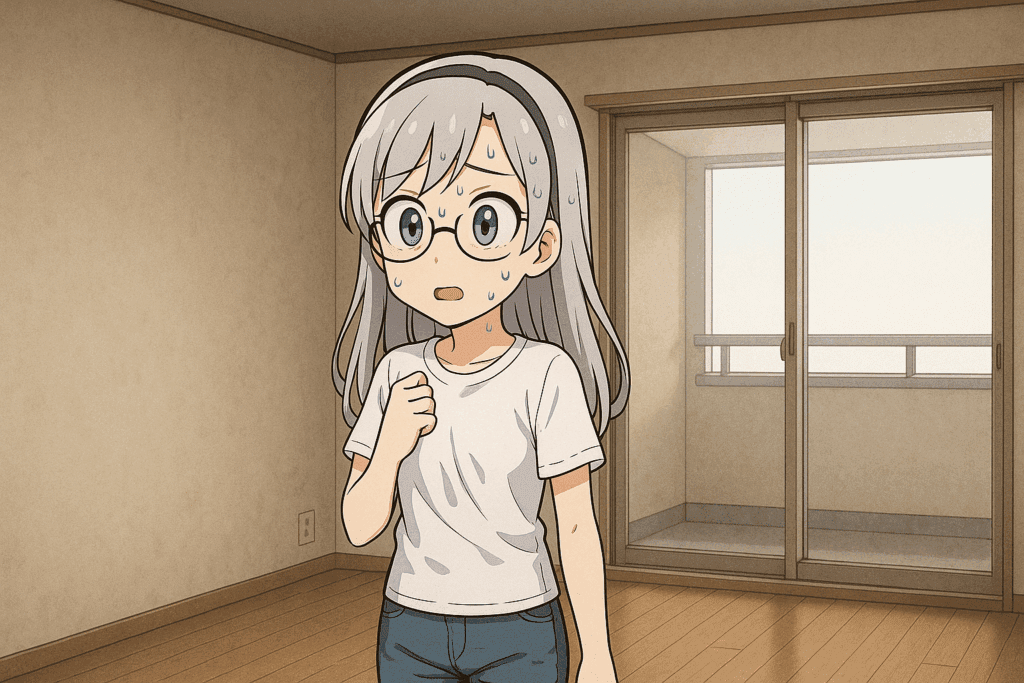
約束の時間は9時だったのに、実際にメンバーが揃ったのは9時半過ぎ。これってうちの会社あるあるですよね。みんな「ちょっと遅れます」のLINEを送ってくるんだけど、結局全員遅刻という。
新事務所は築25年のマンションの3階。エレベーターはあるけど、なんか微妙に狭くて、みんなで荷物持って上がるの大変でした。部屋に入った瞬間の感想は「うーん、思ったより狭い」。でも、大きな窓があって光は入るし、まあ悪くないかな。
先輩の社員食堂のシェフ(27歳)が「ここで10人も撮影するの?」って言ってたけど、私も同じこと思った。物理的に厳しくない?
パウダールーム(って言ってもただの洗面所)に10人が殺到。案の定、鏡の取り合いが始まりました。結さん(26歳)が「私、朝からメイクしてきたから大丈夫です」って言ってたけど、結局みんなと同じように鏡の前で化粧直ししてる。女子って正直だなあ。
さゆりが持参したメイクボックスがプロ級で、みんなから「すごーい」の嵐。私なんてドラッグストアのアイシャドウパレット一個だけ。格差を感じる瞬間です。
洗面所で聞こえてきた会話: 「昨日の合コンの話、どうなったの?」 「あー、あの人?連絡来てないから脈なしかも」 「でも写真は盛れてたよね」
朝からこのテンション。今日一日が思いやられる…。
ここで予想外の真実が発覚!!
鏡に殺到したのは「本当は誰も化粧していなかった」
みんな「普段より少しだけおしゃれ」な服装で来てるはずなのに、なぜか更衣室(元々の寝室)で着替え大会が始まりました。麻紀なんて、スーツケース一個分の衣装を持参。「迷っちゃって」って言ってるけど、明らかに気合入りすぎでしょ。
(仕事以外はトレーナーにジーパンが多い麻紀)
私は無難に白いブラウスとネイビーのタイトスカートにしたんだけど、みゆきに「みくちゃん、それ地味すぎない?」って言われてちょっとムッとした。でも確かに、他のみんなと比べると保守的かも。
かずみの花柄ワンピースは本当に可愛くて、思わず「どこのブランドですか?」って聞いちゃった。「ZARA」って答えてくれたけど、私が着ても絶対似合わないやつ。体型の差って残酷。
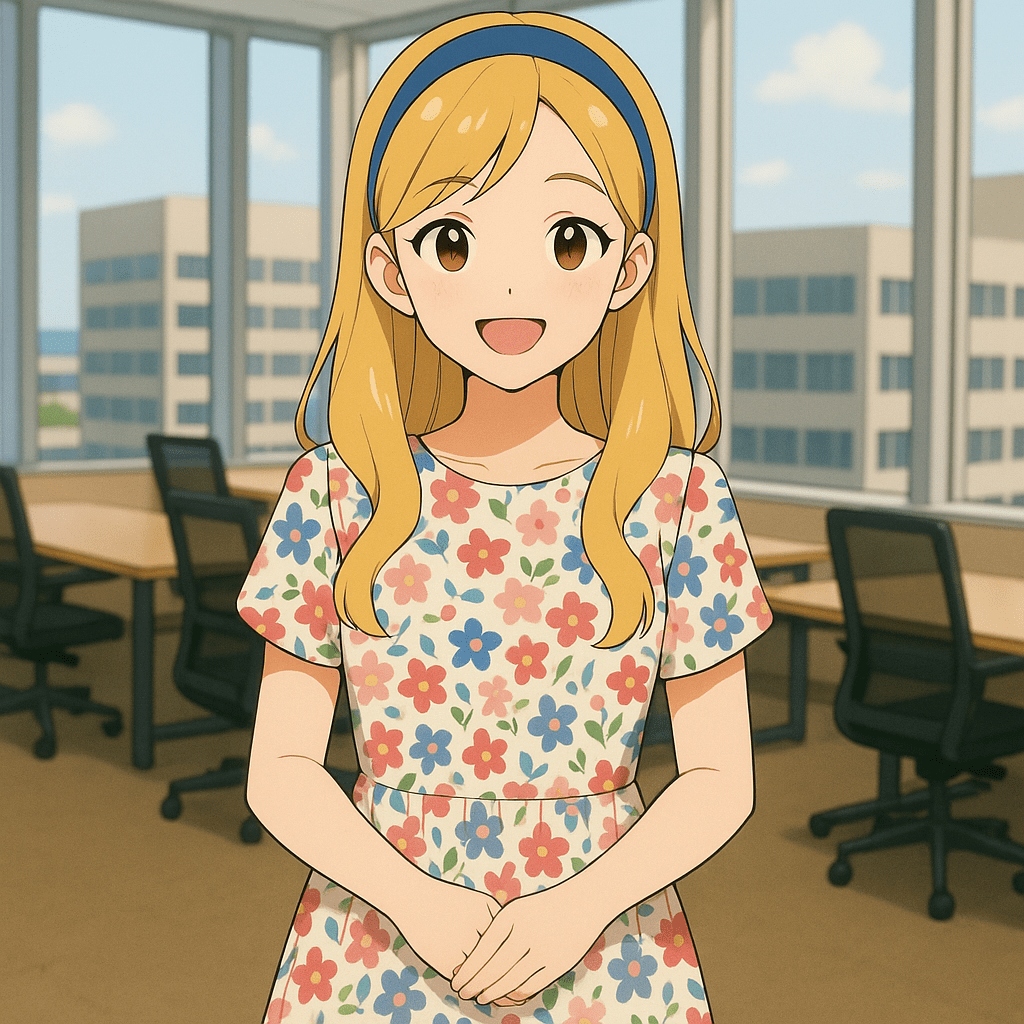
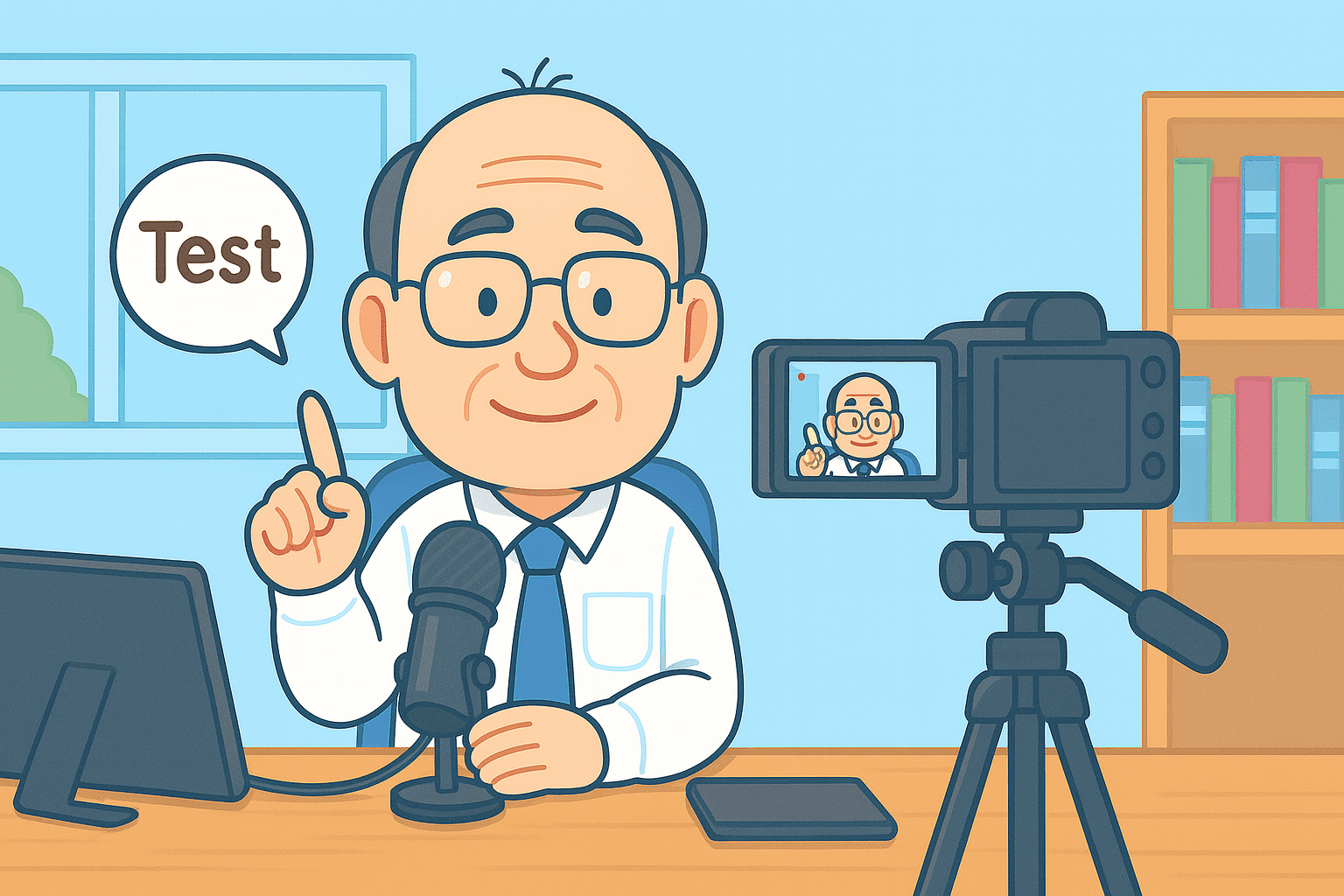
撮影を任されたやすさん、最初はプロフェッショナルな感じだったんだけど、だんだん表情が曇ってきました。理由は明らか。狭い部屋に10人の女性が入ると、物理的に撮影が難しいんです。
「えーっと、もう少し後ろに下がっていただけますか」 「そちらの方、少し左に…あ、でも壁があるので無理ですね」
やすさんの困った顔を見てると、なんだか申し訳なくなってきました。でも、これって事前に分かってたことじゃない?なんで会社は下見しなかったんだろう。
休憩時間に麻紀がコーヒーを飲もうとして、手が滑って隣にいた夢子の白いシャツにぶちまけてしまいました。
「きゃー!」「大変!」「誰かタオル!」
みんなで大騒ぎ。でも正直、私はちょっとホッとした部分もありました。だって、緊張してた空気が一気に和んだから。夢子も最初は「えー」って顔してたけど、みんなが必死に対処してくれるのを見て笑ってました。
「まあ、こういうこともあるよね」
この一言で、現場の空気が完全に変わりました。
濡れたシャツ事件をきっかけに、なぜか「完璧な撮影」から「面白い撮影」にコンセプトが変更。誰が決めたわけでもないのに、自然とそうなってました。
リビングにあった観葉植物(前の住人が置いていったやつ)を使って「オフィスジャングル」なるものを作成。みんなで植物の葉っぱを持ってポーズ。客観的に見ると完全におかしいんだけど、その時は楽しくて仕方なかった。
ゆり先輩が「私たち、何してるんだろうね」って笑いながら言ってたのが印象的。でも、誰も止めようとしない。むしろエスカレートしていく一方。
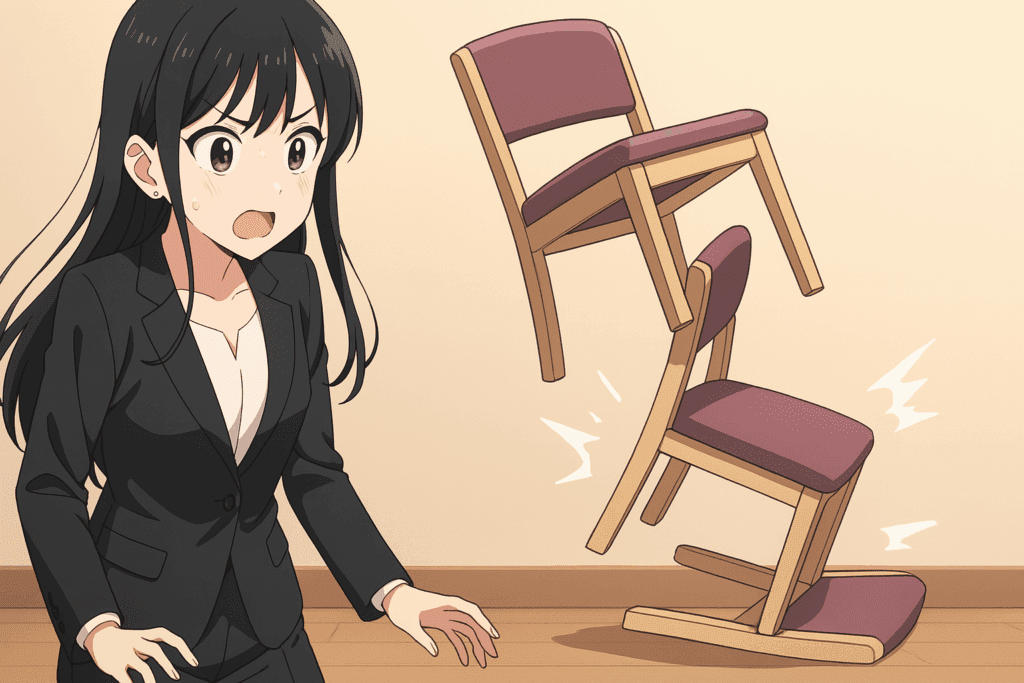
狭い部屋で「高さ」を出すために、折りたたみ椅子を3段重ねにして撮影することになりました。今思えば、明らかに危険だったんですが、その時は誰も冷静じゃなかった。
案の定、椅子が崩れて結ちゃんが床に座り込む形に。幸い怪我はなかったけど、スカートがめくれ上がって…。田中さんが慌てて目を逸らしてたのが印象的でした。
「大丈夫?」「怪我してない?」
みんなでユイちゃんを心配したんだけど、本人は「恥ずかしい」って顔を真っ赤にしてました。可愛いなあ、22歳。私もあの頃はもう少し可愛らしい反応してたのかな。
一番盛り上がってる時に、なぜか社長が突然現れました。事前連絡なし。みんな一瞬フリーズ。
「楽しそうですね」
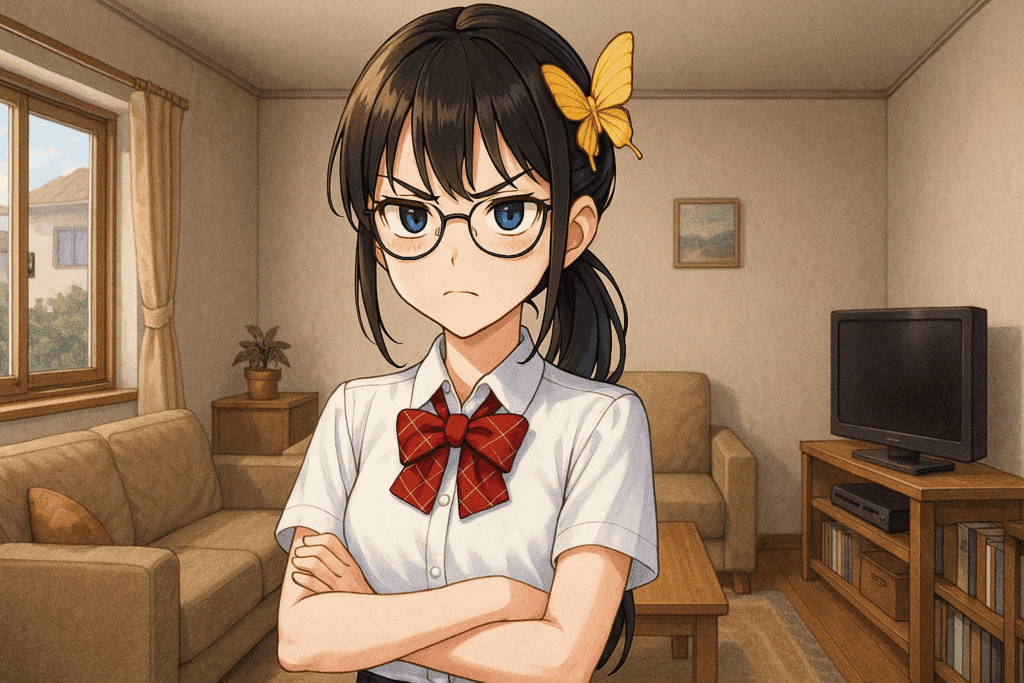
「やばい!!」
全員が凍り付いた…
社長は穏やかな口調だが目が怒っている💦
「皆、今日はリミブレイクのプロフ用の写真撮影でしょ?それが、なぜ…私服なのかしら?」
「それは…」
一同は下を向いてしまった。
「それにね、すっぴんで職場に来るとは何事なの?それとも…」
社長がにやりと笑った。
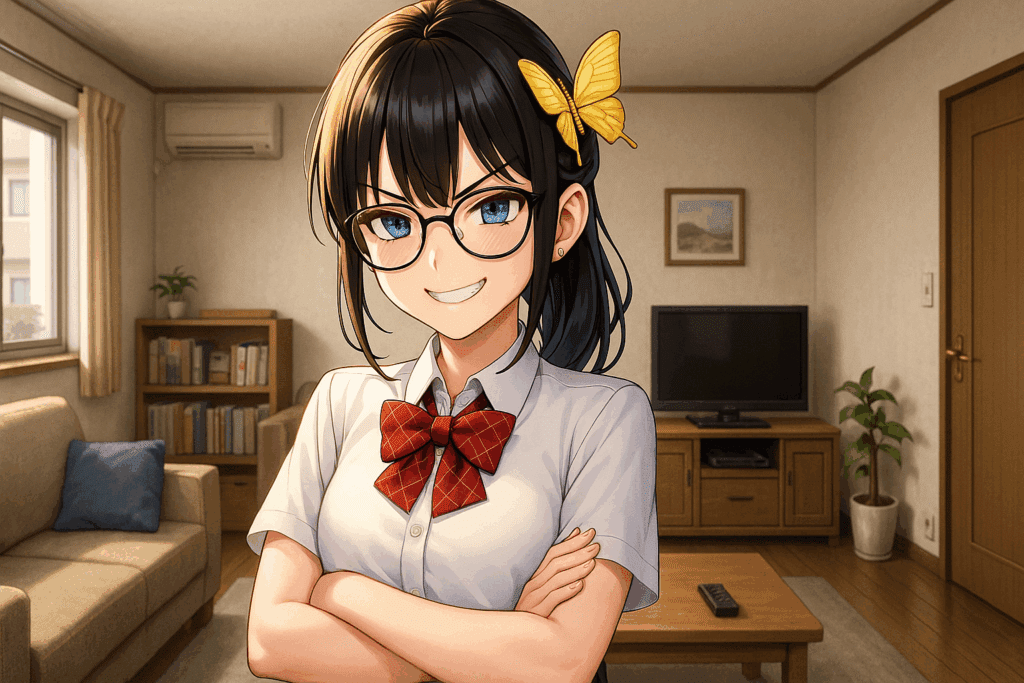
「げっ!!!」
社長は「今日からリミブレイクは「下着販売メーカー」に変えようかしら?」
それから鋭い目で
「全員下着で撮影しなさい!!]
「ご、ごめんなさい!!」
「申し訳ありませんでした」でしょう?
「は、はい!!」
私たちは全員、ものすごいスピードでロッカーにしまってあった、オフィスレディの制服に着替えた。
なんだかんだで撮影終了。みんなでお疲れ様のお茶タイム。狭い部屋だから、コンビニで買ったペットボトルのお茶を床に座って飲む感じ。なんか学生みたい。
「今日って何の撮影だったっけ?」ってさゆりさんが言い出して、みんなで爆笑。確かに、最初の目的を完全に見失ってた。
結先輩が「でも、たまにはこういうのも良いよね」って言ってくれて、なんとなくみんなも納得した雰囲気。私も楽しかったのは事実だし。
ゆり先輩と一緒に駅まで歩いてる時に、ぽろっと本音が出ました。
「正直、ちょっと疲れた」 「わかる。でも、みんなで騒げて楽しかったよね」 「うん。ただ、やすさんの視線がちょっと…」 「あー、気になった。でも悪い人ではないと思うけど」
そうなんです。全体的には楽しかったけど、微妙にモヤモヤする部分もあった。特にやすさんの反応とか、写真をどう使うのかとか。そういえば、結さんの婚約者の龍二君。終始無言だったな。私達を見て何も感じないのかな?
シャワーを浴びて、一人になってから今日のことを振り返ってみました。楽しかったのは間違いないけど、「これって本当に会社の広報写真として適切だったのかな?」という疑問も湧いてきます。
SNSで「映える」写真を撮ることが重視される時代だから、こういう企画になったんだと思うけど、私たちって「商品」扱いされてない?そう考えると、ちょっと複雑な気持ちになります。ゆりさんの「イメージガールは「見せてなんぼ。芸は売っても身は売るな」」の言葉が頭に浮かんだ。
そうだ、私も一時はゆりさんにあこがれて、イメージガールを目指してここに来た。あの頃から、私のあこがれはゆりさんだった。だから、今回の撮影も「商品扱い」ではないはずだ。もし、そうならゆりさんが黙ってはいないだろう。
「これでいいんだよね…」
でも、普段は事務作業ばかりで、みんなでワイワイする機会って意外と少ないから、そういう意味では良い機会だったかも。麻紀ちゃんなんて、普段はおとなしいのに今日は積極的だったし。
明日会社に行って、今日の写真を見せられるのがちょっと心配。やすさんがどんな写真を選んで、どう加工するのか。私たちの「素」の部分まで写っちゃってるかもしれないし。
それと、他の部署の人たちにどう説明すれば良いのかも悩みどころ。「撮影会楽しかった」って言うのは簡単だけど、実際は結構カオスだったし。
今日一日を通して感じたのは、会社のイベントって「建前」と「本音」のバランスが難しいなということ。最初は「きちんとした広報写真を撮りましょう」っていう建前だったのに、気がついたら本音の部分が全面に出てしまった。
でも、それが必ずしも悪いことだとは思いません。普段見えない同僚の一面を知ることができたし、チームワークも深まった気がします。ただ、境界線は大切だなとも思いました。
明日、会社でみんなとどんな話をするのか、今から楽しみです。きっと「昨日は大変だったね」って笑い話になるんだろうな。
そして、次回もし同じような企画があったら?正直、微妙なところです。楽しかったけど、もう少し計画的にやりたいかも。
追記: 結先輩からLINEで「お疲れさまでした!楽しかったです」って送られてきました。みんな同じ気持ちなのかな。明日が楽しみです。