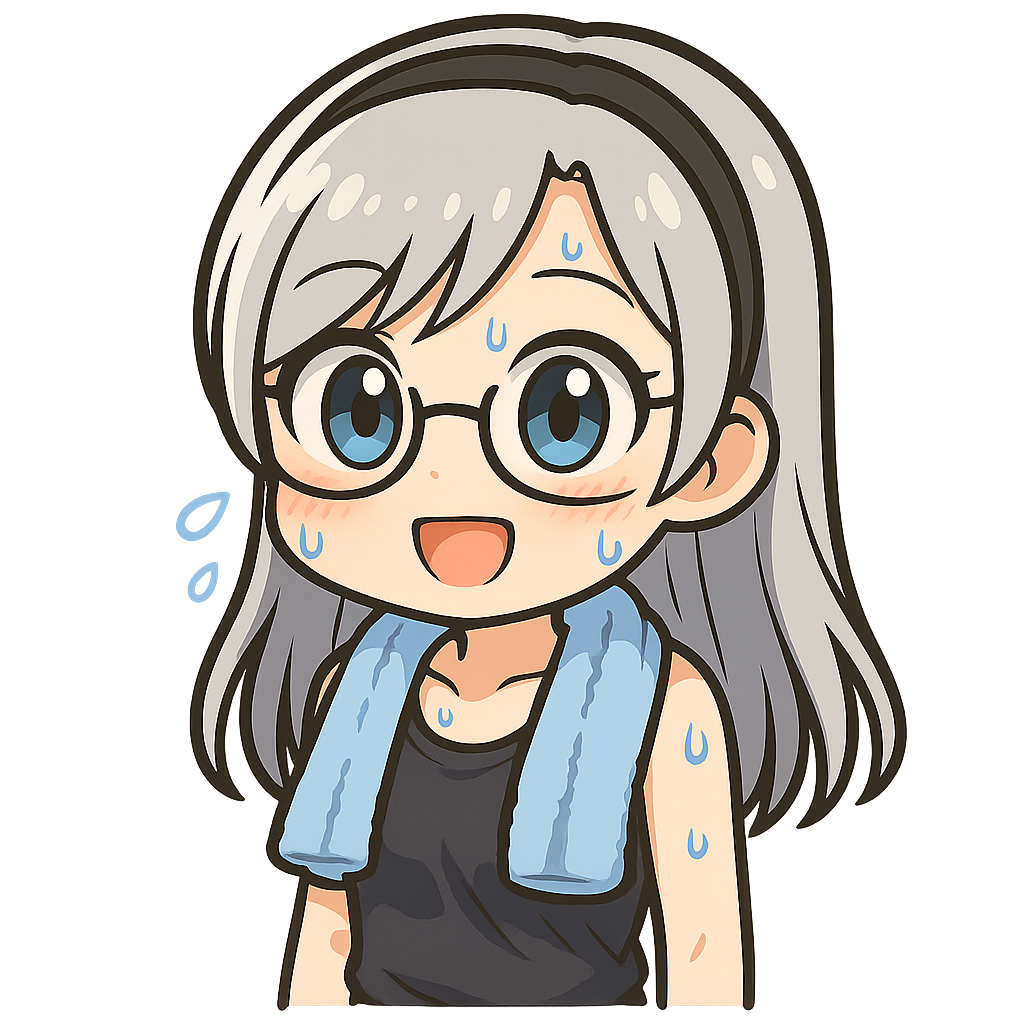こんにちは、佐々木優です。私がIT企業を起業してから8年が経ちました。この間、日本のデジタル社会は目まぐるしく変化し、特に2025年に入ってからその変化は加速度を増している、というのが現場にいる私の実感です。
今日は、これから社会に出る皆さんに向けて、今のデジタル社会で実際に何が起きているのか、そしてこれからどう変わっていくのかをお話ししたいと思います。統計や白書に書かれていることももちろん大切ですが、それ以上に現場で感じている生の情報をお伝えできればと思っています。
AIの進化が想像以上に早い理由
私たちが目の当たりにしているAIの変化
正直に言うと、AIの進化スピードには私自身も驚いています。2022年にChatGPTが話題になった時、「これは面白いツールだな」程度に思っていたんです。でも2025年の今、状況は全く違います。
先日、Googleの「NotebookLM」を実際に使ってみたのですが、これには本当に驚かされました。2025年6月4日にノートブックをパブリックリンクとして誰とでも共有できる新機能が提供開始され、そして7月14日にはThe EconomistやThe Atlanticといった有名メディアと連携した「Featured Notebooks(おすすめのノートブック)」という厳選されたノートブック集が公開されるようになりました。この機能によって、信頼性の高い専門的な情報にAIを通じてアクセスできるようになったんです。
私の会社でも、昨年から生成AIの活用を本格的に始めています。最初は「効率化のツール」として考えていたのですが、今では業務の進め方そのものが変わってきています。単純な作業の自動化だけでなく、アイデア出しや企画書の初期案作成、さらには顧客とのコミュニケーションまで、AIが支援してくれる範囲がどんどん広がっているんです。
大手企業の取り組みから見えること
LINEヤフーが2025年7月14日に全従業員約11,000人を対象に業務における生成AI活用の義務化を前提とした新しい働き方を開始すると発表し、3年間で業務生産性を2倍にするという目標を掲げたニュースを見た時、「ついにここまで来たか」と思いました。私たちのような中小企業でも、もう「AIを使うか使わないか」ではなく、「どう使いこなすか」の段階に入っているということです。
LINEヤフーの取り組みで特に注目したのは、従業員の業務の3割を占める「調査・検索」「資料作成」「会議」という共通領域から着手している点です。これって、どの会社でも共通する課題なんですよね。「まずはAIに聞く」を基本原則として、ゼロベースの資料作成を禁止し、必ずAIでアウトラインを作成してから始めるルールを設けているそうです。
特に興味深いのは、大規模なLLM(大規模言語モデル)だけでなく、Microsoftの「Phi」シリーズのような小規模なモデルも注目を集めていることです。140億パラメータの「Phi-4」は、複雑な推論に対応しながらも軽量で高速処理が可能。これって、私たちのような企業にとってはすごく実用的なんです。
なぜかというと、巨大なモデルを使うにはコストがかかりすぎるし、社内の機密情報を外部のサービスに送るのは不安だからです。でも小規模なモデルなら、社内のサーバーで動かせるし、コストも抑えられる。実際、私たちもローカル環境で動く小規模モデルの導入を検討しているところです。
NTTグループの技術開発が示すもの
NTTグループがLLMの追加学習なしで決められた長さ以上のテキストを生成できる技術を開発したというニュースも、現場目線では非常に重要です。学習コストの削減って、私たちのような企業にとっては死活問題なんです。
私が起業した当時、最新技術を使おうと思ったら、とにかくお金がかかりました。でも今は、効率的な技術開発によってコストが下がり、中小企業でも最先端の技術を活用できるようになってきています。これは本当にありがたいことです。
Web3とコンテンツ産業の新しい波
Web3の分野では、従来のように大企業が巨額の資金を投じてコンテンツを作る時代から、個人クリエイターが小さく始めて大きく育てる時代に変わってきています。
私の知り合いにも、NFTアートで収益を上げているクリエイターがいます。彼らの話を聞いていると、技術的なハードルが下がったことで、アイデアさえあれば誰でもチャレンジできる環境が整ってきていることを実感します。
特にYahoo!きっずの「AIでゲームつくりエイター」サービスは、子どもたちにとって素晴らしい学習機会だと思います。2025年7月11日にサービス開始されたこの取り組みでは、生成AIを活用した5種類のゲームを通して、プロンプトの書き方や設計方法を楽しく学べます。私が子どもの頃は、プログラミングといえば専門的で難しいものでした。でも今の子どもたちは、AIを使いながら自然にゲーム制作を学べる。これは本当にうらやましいです。
量子コンピューターの実用化が目前に
富士通と理研の成果が意味すること
富士通と理化学研究所が2025年4月22日に256量子ビットの超伝導量子コンピューターを開発したニュースは、IT業界にいる私たちにとって本当にエキサイティングな出来事でした。量子ビットの集積化、極低温状態を保つ熱設計、高密度実装…これらの技術的課題を日本の研究機関が克服したということは、我が国の技術力の高さを示していると思います。
私は大学時代に量子力学を少し勉強しましたが、正直言ってとても難しくて「こんなものが実用化されるのはずっと先の話だろう」と思っていました。でも2025年になって、HPCとの融合による実用化が現実味を帯びてきています。
この256量子ビットマシンは、外部ユーザーに提供されている超伝導量子コンピューターとしては世界最大級で、2025年度第一四半期中に企業や研究機関に向けて提供が開始される予定です。3次元接続構造により、64量子ビット機から容易に大規模化できることも実証されました。
セキュリティへの影響と対策
ただし、量子コンピューターの実用化は、サイバーセキュリティの観点では大きな課題でもあります。現在の暗号技術が危殆化する可能性があるからです。総務省が量子暗号通信技術の研究開発を2025年度から本格的に推進しているのも、この危機感の表れだと思います。
私たちのような企業も、将来的には量子暗号に対応したセキュリティシステムへの移行を考えなければならないでしょう。技術的な詳細はまだ完全に理解できていませんが、盗聴を確実に検知できる量子の物理的特性を活用した技術というのは、本当に革新的だと思います。
サイバーセキュリティの現実的な脅威
現場で感じる脅威の変化
サイバー攻撃について話すと、「自分の会社は大丈夫」と思われる方もいるかもしれません。でも実際には、規模に関係なくどの企業も標的になり得るのが現実です。
私の会社でも、昨年だけで複数回、怪しいメールや不審なアクセスを確認しました。幸い大きな被害はありませんでしたが、常に緊張感を持って対策を講じています。情報通信研究機構(NICT)の観測では、IoT機器を狙った攻撃が全体の約3割を占めているという報告もあります。
特に気になるのは、2025年の大阪・関西万博前後にサイバー攻撃が増加する可能性が指摘されていることです。関西の中小企業が狙われる懸念もあり、私たちも他人事ではありません。
法整備の進展と実務への影響
2025年5月16日に「能動的サイバー防御法案」が参院本会議で可決・成立し、同年5月23日に公布されたことは、企業経営者として非常に心強く感じています。国や重要インフラの安全確保に向けた政府の本気度が伝わってきます。
この法律により、国による通信監視や官民の情報共有で攻撃の予兆をつかみ、警察と自衛隊が無害化する措置を取れる体制が構築されます。基幹インフラ事業者には報告義務も課せられることになりました。
ただし、法律ができたからといって、企業側の責任が軽くなるわけではありません。むしろ、これまで以上にセキュリティ対策への取り組みが求められるようになると考えています。
IPAのサポートを活用した実体験
情報処理推進機構(IPA)の「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、私たちのような中小企業にとって本当にありがたい存在です。ワンパッケージで安価にセキュリティ対策を提供してくれるので、限られた予算の中でも適切な対策を講じることができます。
実際に相談窓口を利用したこともありますが、専門的なアドバイスを分かりやすく説明してもらえました。Oracle JavaやMicrosoft製品の脆弱性情報も定期的に更新されているので、常にチェックするようにしています。
セキュリティ人材不足の深刻さ
これは本当に深刻な問題です。私の会社でも、セキュリティに詳しいエンジニアを採用しようとしていますが、なかなか見つからないのが現実です。技術の進歩に比べて、それを理解し適切に運用できる人材の育成が追いついていません。
総務省がNICT(情報通信研究機構)を通じて「CYDER」(実践的サイバー防御演習)や「SecHack365」といった育成プログラムを推進していることは素晴らしいと思います。でも、それでもまだ圧倒的に人材が不足している状況です。
新社会人の皆さんには、ぜひセキュリティ分野にも興味を持ってもらいたいです。技術的に挑戦的で、社会的意義も高く、需要も非常に大きい分野です。
デジタル化による社会課題解決の可能性
行政サービスの変化を実感
マイナンバーカードの普及率が2025年2月末時点で78.0%(約9,700万枚)に達したというニュースを見た時、「ようやくここまで来たか」という感慨がありました。私自身、確定申告でe-Taxを使っていますが、紙の書類で手続きしていた頃と比べると、本当に楽になりました。
法人税申告の86.2%、所得税申告の69.3%がe-Taxを利用しているという数字も、デジタル化の浸透を示していると思います。ただし、まだ完全にペーパーレスになったわけではなく、一部の手続きでは依然として紙の書類が必要な場合もあります。
地方でのデジタル活用事例
北海道帯広市のスマート農業の実証事業には、大きな可能性を感じています。2024年度に「帯広市川西農業協同組合(JA帯広かわにし)」が中心となって総務省「令和6年度地域デジタル基盤活用推進事業」の実証事業を活用し、ドローンとAIを組み合わせて作物を管理したり、複数の無人トラクターを同時に動かしたりする実証試験が行われました。人手不足が深刻な農業分野でのデジタル活用は、まさに課題解決の好例だと思います。
私の実家も地方にあるのですが、高齢化が進んで農業の担い手が減っているのを目の当たりにしています。こうした技術が普及すれば、少ない人数でも効率的に農業を続けられるようになるかもしれません。
京都府京丹波町の「京丹波GREEN Pay」のようなデジタル地域通貨も興味深い取り組みです。地域経済の活性化にデジタル技術を活用するという発想は、多くの地方自治体が参考にできると思います。
防災・減災への応用
2024年1月の能登半島地震での教訓を受けた放送ネットワークの強靱化支援は、非常に重要な取り組みだと感じています。災害時にテレビ放送が重要な情報源になることは、私自身も東日本大震災の時に痛感しました。
携帯電話基地局の停電対策強化、移動基地局、無人航空機、低軌道衛星等の活用拡充など、通信ネットワークの強靱化も進んでいます。私たちのようなIT企業も、BCP(事業継続計画)の一環として、これらの動向をしっかりと把握しておく必要があります。
働き方の変化:リモートワークの現実
エンジニアのリモートワーク実態
これは私自身の経験からも言えることですが、エンジニアの働き方に関する調査結果は、現場の実感とよく合っています。「ハイブリッド型勤務」が半数以上、「フルリモート勤務」が約3割という数字は、私の周りのエンジニアの状況ともほぼ一致しています。
私の会社でも、コロナ禍をきっかけにリモートワークを導入しましたが、今ではそれが当たり前になっています。フルリモート勤務の満足度が9割以上という調査結果も納得できます。実際、リモートワークによって通勤時間がなくなり、集中して作業できる環境を整えやすくなったというメンバーが多いです。
出社義務化への抵抗感
フルリモートから出社義務化を経験したエンジニアの約7割が受け身の姿勢を示し、約2割は仕事を続けられないと感じるという調査結果には、正直驚きました。でも、実際に私の知り合いのエンジニアからも似たような話を聞くことがあります。
出社に抵抗を感じる理由として「通勤が負担になる(46.7%)」「リモート勤務の方が生産性が高い/集中できる(45.0%)」「ワークライフバランスが悪化する(35.2%)」が挙げられていますが、これらは本当にその通りだと思います。
私自身、創業当初は「みんなで同じオフィスにいることで一体感が生まれる」と考えていました。でも実際にリモートワークを経験してみると、必ずしもそうではないことが分かりました。大切なのは、働く場所ではなく、いかに効率的に成果を出すかということです。
柔軟な勤務形態の重要性
エンジニアが出社を受け入れられる条件として「出社日が柔軟に選べる(ハイブリッド型勤務)」が49.3%で最も多いという結果は、現場の感覚とも合っています。私の会社でも、完全にリモートにするのではなく、必要に応じて出社できるハイブリッド型を採用しています。
「出社は短期・一時的」(39.5%)、「勤務時間の自由度(フレックスタイム制や短時間勤務など)」(36.7%)という条件も理解できます。プロジェクトの状況やチームの連携が必要な時だけ出社して、普段は各自が最も生産性の高い環境で働く。これが理想的な働き方だと思います。
産業・市場の変化と課題
クラウドサービス市場の拡大
世界のパブリッククラウドサービスの売上高が2024年に7,733億ドルに増加したという数字を見ると、この市場の巨大さと成長力を改めて実感します。Amazon、Microsoft、Googleが大きなシェアを占めているのは、私たちのような企業でも実感するところです。
私の会社でも、これらのクラウドサービスを活用していますが、その便利さと同時に、海外事業者への依存という課題も感じています。データの保存場所や管理方法について、経営判断として慎重に検討する必要があります。
国内市場の課題と可能性
国内のAIOps/運用自動化市場が2024年度に20%弱の成長を見込んでいるという予測は、運用効率化への需要の高まりを示していると思います。私たちのような中小企業でも、人手不足を補うために自動化への投資を検討しています。
ただし、日本のデジタル分野の国際競争力が低いという課題は深刻です。デジタル関連サービスの国際収支の赤字拡大は、国全体として取り組むべき問題だと感じています。
ITreviewによる製品評価の重要性
「ITreview Grid Award 2025 Summer」で約1,230製品・サービスが評価されたというニュースは、IT選定の参考になります。私たちが新しいツールやサービスを導入する際も、実際のユーザーレビューを重視しています。
特にB2B向けのIT製品は、実際に使ってみないと分からない部分が多いです。ユーザーのリアルな声が集約されているプラットフォームは、本当に価値があると思います。
NTTグループの多岐にわたる取り組み
NTTグループの取り組みを見ていると、単なる通信事業者を超えて、社会課題解決に幅広く貢献していることが分かります。
新潟大学との遠隔触診技術の共同研究は、医師不足・偏在という地域課題の解決に直結する取り組みです。私の実家がある地方でも、専門医不足は深刻な問題になっています。こうした技術が実用化されれば、多くの人が助かると思います。
鋼材を使用したインフラ施設の画像から腐食の進行を予測する技術も、保全コスト削減に大きく貢献するでしょう。日本のインフラの老朽化は深刻な問題ですから、AIを活用した効率的な保守管理は必要不可欠です。
生物多様性ビッグデータを運営する株式会社バイオームへの出資や、衛星画像データによる植生および生物の広域推定技術の開発など、環境分野への取り組みも印象的です。企業活動と環境保護の両立は、これからの時代に不可欠な視点だと思います。
2025年大阪・関西万博への期待
NTTパビリオンの取り組みや、「つながるっ展」のようなイベントを見ていると、万博への期待が高まります。私も実際に万博会場を訪れる予定ですが、最新のデジタル技術が一堂に会する貴重な機会だと思っています。
万博は単なるイベントではなく、日本の技術力を世界に示すチャンスでもあります。特にデジタル分野での競争力向上のきっかけになればと期待しています。
新社会人へのメッセージ
これまで長々とお話ししてきましたが、新社会人の皆さんに伝えたいことは、「変化を恐れずに、積極的に新しい技術に触れてほしい」ということです。
私が社会人になった頃と比べて、今は本当に多くの可能性が開かれています。AIや量子コンピューター、Web3など、SF映画の中でしか見たことがなかった技術が現実のものになっています。
一方で、サイバーセキュリティのような課題も深刻化しています。でも、これらの課題があるからこそ、皆さんのような若い世代の力が必要なんです。
具体的なアドバイス
- 継続的な学習を心がけてください
技術の進歩は早く、大学で学んだことがすぐに古くなってしまうこともあります。でも、基礎的な考え方や問題解決のアプローチは変わりません。常に新しいことを学ぶ姿勢を持ち続けてください。
- 失敗を恐れないでください
私も起業してから多くの失敗をしました。でも、その失敗があったからこそ、今の会社があります。特にIT分野では、失敗から学べることがたくさんあります。
- 人とのつながりを大切にしてください
リモートワークが普及して、直接会う機会は減りましたが、人とのつながりの重要性は変わりません。同僚や先輩、業界の人たちとの関係を大切にしてください。
- 社会課題に関心を持ってください
デジタル技術は手段であって、目的ではありません。その技術を使って何を解決したいのか、社会にどう貢献したいのかを考えてみてください。
おわりに
2025年のデジタル社会は、まさに激動の時代です。AI、量子コンピューター、Web3といった技術革新がある一方で、サイバーセキュリティや人材不足といった課題もあります。
でも、こうした変化の時代だからこそ、新しいアイデアや若い力が求められています。皆さんには、既成概念にとらわれることなく、自由な発想でこの変化に立ち向かってほしいと思います。
私自身、まだまだ学ぶことがたくさんありますが、これからも現場の視点を大切にしながら、日本のデジタル社会の発展に貢献していきたいと考えています。
新社会人の皆さんの活躍を心から応援しています。一緒にこの変化の波を乗り越えて、より良いデジタル社会を築いていきましょう。
佐々木 優
参考資料・出典
主要な出典元
技術・法制度関連
サービス・製品情報
農業・地方創生関連
セキュリティ・法制度関連
政府・行政関連
本記事は現在入手可能な公開情報に基づいて作成されており、各種データや事実については上記の信頼できる情報源から引用しています。技術の進歩は日々続いているため、最新の情報については各公式サイトをご確認ください。